vol.24 セザンヌのリンゴ
静物画でよく描かれるものの代表格と言えばリンゴ。そしてリンゴの静物画と言えば、フランスのエクス=アン=プロヴァンス出身の画家ポール・セザンヌです。ポスト印象派とも言われたスタイルで、のちのキュビズムなどにも影響を与えたため「近代美術の父」と称される、あのセザンヌ。彼は生涯で60以上もの「リンゴを描いた」作品を残し、「リンゴ一つでパリを驚かせてみせるぞ」という名言もあります。
いったい何がセザンヌをしてそこまでリンゴという題材にのめり込ませたのかはよくわかりませんが、当時のフランスではリンゴが手に入りやすかっただろうということは想像できます。なかなかお目にかかれないものを微に入り細を穿つようにして描写することは難しいでしょう。リンゴがかんたんに買える環境だったからこそ、セザンヌはいつまでもその描写にトライできたのです。

パリから西にずっと進むと、ノルマンディ地方があります。この地方は、スティーヴン・スピルバーグ監督の『プライベート・ライアン』のリアルで壮絶な冒頭のシーンなど、何度も映画の舞台になった第二次世界大戦のノルマンディー上陸作戦でもよく知られています。つまり、海(英仏海峡)に面しているわけです。この作戦によってノルマンディという地名は世界中の人が知る有名なものになっているのですが、この地域がフランスきってのリンゴの産地だということはフランス人以外の人にはほとんど知られていないでしょう。すみません、僕も調べるまで知りませんでした。
この地方でたくさん採られたリンゴがどのように活用されているのかは、ライターの加納雪乃さんがりんご大学内の連載「Bonjour! フランスのリンゴ」で一昨年に書かれた記事が詳しいのでそちらをぜひご覧ください。連載自体もオススメです!

加納さんがリポートしてくださっているように多彩な加工品が生み出されるほどたくさんリンゴが採れるノルマンディから、セザンヌの住むパリにリンゴが山のように運び込まれ売られていた様子が何となく思い浮かびます。なので、リンゴという題材はある意味ありふれていて、画家を目指す人間が誰でも描いてみようと考えるものだったとも言えると思います。
しかしこういうことも言えるのではないでしょうか。いつでもどこでも誰でも買えるリンゴというものを対象にしたからこそ、セザンヌの独自性が逆に強調されたのではないか。珍しさ、新奇さとは真逆の、リンゴという「当たり前」をどう描くのかという部分に、彼の作家性が凝縮されたのです。
かつて80年代前半に、ウィントン・マルサリスという黒人の天才トランぺッターが非常に話題になりました。クラシックを重点的に学んできた彼は、そのバックグラウンドを最大限活かした超絶技巧でジャズ・ファンにショックを与えます。当時、正確無比な演奏テクニックはクラシック奏者の代名詞で、技術の精緻さという意味ではジャズ・プレイヤーは一段劣ると思われていました。ざっくり言うと「雑」だったのです。もちろん、音楽の価値は一つの視点だけではかれるものではありません。
しかしウィントンはジャズの即興のスリルとクラシック演奏の淀みのない美しさを融合したようなプレイスタイルで、一線を画しました。デビュー当時のバカテクが思う存分楽しめるアート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズ『キーストン3』やキャリア初期の二枚組ライヴアルバム『ライヴ・アット・ブルース・アレイ』などは今も輝きを失わないエヴァ―グリーン的な名盤です。また彼はクラシック作品の演奏家としても一流の実力を持つ、初の「本格派二刀流」プレイヤーとしても名をあげました。
ウィントンが若い頃の自作曲を再び演奏した動画
ちなみに、彼の父エリスも兄ブランフォードも著名なジャズ・ミュージシャンです。特に兄ブランフォードは古くはスティングのバンド・メンバーになったことでポップ・ミュージック・ファンにも広く名を知られるようになり、今は現代ジャズ・シーンの巨匠として尊敬されています。一方でウィントンは、現在ではその評価はけっこう分かれています。彼はある時期から「伝統文化としてのジャズ」「クラシック音楽と肩を並べうるジャズ」の継承に重点を置くようになり、音楽制作のスタンスも発言も「新しい世代の代表」から「保守的なおじさんたち」にシフトチェンジしたように見えたからです。
そんな彼が若い頃、面白いことを言ってました。「最近のミュージシャンやファンは、シンセサイザーなど新しく珍しい楽器を使えばすぐ新しい音楽になると思っている。そんなかんたんなものじゃない。歴史を踏まえて音楽を理解しなければ、新しいものなんて作れないんだ」。まあ、こんな発言を繰り返す彼に対する評価が分かれてしまうのも無理はないと思います。実際、彼が批判するような「軽はずみ」なきっかけから新しいものが生まれる可能性も少なくないですしね。
ただ、読んだ当時は僕も若者だった(笑)ので反感を持ったのですが、セザンヌがリンゴにこだわったという史実を通して見るとちょっとニュアンスが変わってきます。ウィントンはきっと、ジャズの歴史を知る重要性とともに「一見古ぼけたように見える、ありふれた音楽に向き合うことから逃げるな」と言いたかったのかもしれない。自分がクリエイターになったつもりでちょっと想像してみてください。自分の存在価値を知らしめるためにはやはり「誰もやってなかったような新しいコンセプトで行こう」と考えるものではないでしょうか。
手垢のついた、誰もが一度はやったことがあるような当たり前の題材は選ばないはずです。だって、そこで個性を発揮することはとても難しいからです。誰もがやっているネタは、誰もが残せる結果しか生まない。しかし、そこにあえて向き合って個性を確立しなければダメなのだ、とウィントンは言いたかったのではないでしょうか。セザンヌのリンゴのように。新しい楽器や題材で作家性にドーピングをするな、ということなのでしょう。
さて、現在では評価が二分するウィントンですが、その理由はもう一つあると思っています。特にヨーロッパで顕著なのですが、ゼロ年代以降に活躍しはじめたジャズ・ミュージシャンはだいたいクラシックの教育をみっちり受けてきた世代なんですね。クラシック奏者のように巧いとかアカデミックに音楽を理解できる、ということは今では当たり前なんです。かつてまぶしく見えたウィントンの二刀流が、珍しくなくなってしまった。
指揮者、クラシック作曲家としても活躍するポーランドの若手ジャズ・コンポーザー、二コラ・コウォジェイチクのコンテンポラリーなジャズコンチェルト
それは日本も同様で、グラミー賞にノミネートされた作曲家の挾間美帆(小学生の頃、青森市に住んでいました!)や石若駿、小田朋美、小西遼など、音大や芸大で音楽を学んだ若手がジャズの道を選び、最先端の音楽家として評価されているのです。ただ、ウィントンはある意味このような時代の到来の何十年も前に「二刀流」を実現した先駆的な存在だったわけで、偉大なミュージシャンであることは間違いないでしょう。
どこにでもあるリンゴという存在は、芸術家にとってはある意味一番チャレンジしがいのある題材なのかもしれません。そんなことを考えながら食べると、いつもと違う味がするかもですね。
2020/1/15
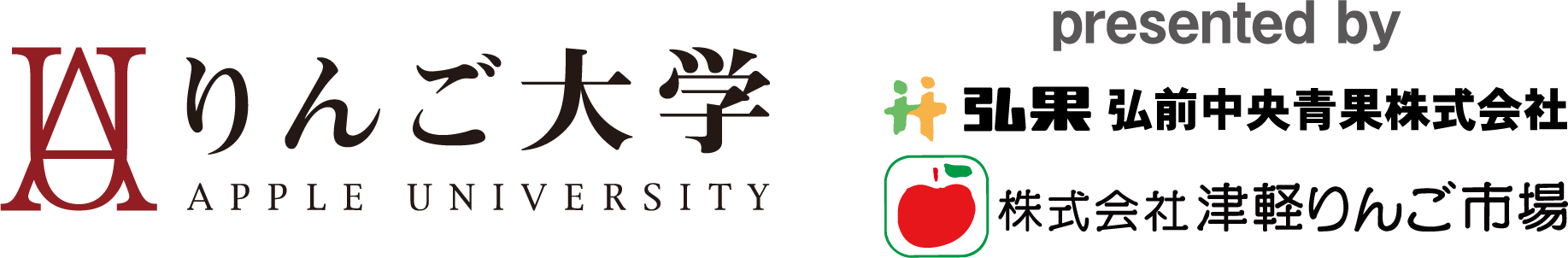

 繁体中文
繁体中文 簡体中文
簡体中文 English
English




