vol.14 楽器になったリンゴやあれこれ
リンゴをかじる音って気持ち良くないですか。ものを食べている音というのはしばしば「下品だ」として避けられがちなトピックです。かつて大女優の高峰秀子は「飯食いシーンに私は出ない」と公言していました。実際は、よく出演していた成瀬巳喜男の作品などで彼女の食事シーンがいくつかありますが。食べる音というと伊丹十三監督のグルメ映画『タンポポ』の食事のマナー教室のシーンなんかも思い出されますね。

嫌われがちな「食べる音」ですが、リンゴや梨など硬いものを食べる響きだけは違うような気がします。さくさくの揚げたてのアジフライとかもそうでしょうか。そのように感じるアーティストがたくさんいるのでしょう。ときどきリンゴの音は音楽作品の中に登場し、その存在感をアピールしています。音楽の世界ではリンゴに限らず「楽器以外のものから生まれた音」が重要な役割を果たすことがあるんですよ。今回はそんなテーマで書きたいと思います。
音楽史上最も有名なリンゴはこれかも知れません。
70年代の世界音楽を代表するバンドAREA(アレア)の傑作ライヴ盤で演奏された代表曲「La Mela di Odessa オデッサのリンゴ」の最中にかじられるリンゴ。むしゃむしゃ
楽器を弾いたら音楽が生まれる。この単純な公式は、実は今の音楽シーンでは過去のものになりつつあります。どういうことでしょうか? まず、一般的には楽器と思われていないものを「演奏」する人が増えました。ジャンルにもよるのですが、最近の音楽CDのクレジットを見ていたら、参加メンバーの中に「DJ」となっている人が目につくようになっています。DJと言うと私も時々やるのですが、その役割を知らない知人たちがよくラジオのディスクジョッキー(パーソナリティー)と勘違いするようです。つまり、DJって案外どういうことをやるのか知られていないようなのです。なので、ここにかんたんに書きます。
パーソナリティーのように喋る方じゃないDJはおおまかに分けて2種類あります。1つは、私がよくやっている「リアルタイム選曲家」としてのDJです。持ってきたCDやレコードをその場で選んで次々とかけていき、カフェやバーのBGMを作ります。やっていること自体はジャズ喫茶の選曲係とあまり変わらないのですが、そちらはあくまでお店のコンセプトに沿う形で、裏方としてかける音楽を選びますが、DJはその選曲を目当てにお客さんが来るということが多いので、個人のセンスを売りにしている点が少し違います。
さて、アーティストのクレジットでDJとなっているのはもうひとつの方です。レコードやCDに録音された音源を、スクラッチやループなどのさまざまなテクニックを使ってアドリブでミックスしトラックを作り出すのです。最初に書いたように、音楽好き以外の人にはまだ認知度は高くないのですが、何十年も前から、音楽を録音したレコードやCDそれ自体も楽器になってしまうという時代に突入しているのです。最近はパソコンにつないだり、カセットテープを使ったりさらに多様化してきています。
ポーランドのDJ二人組スカルペルです。
使う音源は60~70年代のポーランドのジャズばかりというこだわりが評判を呼んで、世界的に有名になりました。
一緒に弾いているピアニストは、現代ポーランドで代表的な若手ピアノフーリガン
現代の面白いところは本当に「楽器がひとつも弾けないミュージシャン」がいるということです。作曲家と言うべきでしょうか。この人たちはテクノロジーの進歩に伴い、パソコンやシンセサイザーを駆使して作曲・録音し、自分では一切楽器を触らずに一つの作品を作り上げてしまいます。非常に大きな括りで「電子音楽」と呼ばれるジャンルですが、黎明期はそれらの作曲家はほぼ全員卓越した演奏家でもありました。例えば昨年亡くなった冨田勲はこの分野の先駆者の代表的な存在ですが、彼はちゃんとアカデミックな教育を受けた、一般的なイメージという意味での作曲家でした。つまり、ピアノも弾けるし音楽理論を学問として修めています。シンセサイザーやシーケンサーを駆使したテクノポップで世界を熱狂させたYMOの3人(坂本龍一、細野晴臣、高橋幸宏)は全員日本の音楽史に残る達人です。
日本のポップ・ミュージック史に輝く名ユニットPSY・S(サイズ)の名曲「Brand-New Menu」。
CHAKAのヴォーカル以外の全ての音を、松浦雅也がシンセサイザーを使って「打ち込み」で作っています。
「楽器の多重録音」ではないところがミソなのですが、松浦自身は複数の楽器を操るマルチプレイヤーで優れた演奏家でした
しかし、テクノロジーの進歩は常に「家庭への普及」にたどり着きます。シンセサイザー、パソコン、インターネット、ミキサーなどがどんどん安価で操作しやすくなってくると、大学で音楽を専門に学んだことがなかったり、楽器を触ったこともない人もそれらを使って作曲ができるようになったんです。そうして裾野が広がった中から、素晴らしい作曲家が次々と登場しました。農業や漁業、料理など職人芸が必要不可欠な世界からしたらこれはあり得ない事態だと思います。音楽はその意味で、テクノロジーの発展とともに「技術」のあり方が変わる、非常に特殊なジャンルだと言えます。
そんな現代の音楽事情に欠かせないのが「サンプリング」という手法です。この言葉にも最初にご説明したDJ同様、大まかに分けて2つの意味があり、一つはレコードなどから曲の一部をカットして取り出し、いろいろなテクニックを使って自分の楽曲や演奏に引用することを指します。もう一つは楽器などさまざまなものから生まれる音を録音・加工して楽曲制作の素材として使用する手法のことです。この「さまざまなもの」には自然音や動物の鳴き声なども含まれます。
後者は最初、非常に実験的な「ミュージック・コンクレート」という現代音楽の一分野として発展しましたが、やがてポップ・ミュージックの中にも取り込まれていきました。楽器以外のものが生み出す音色に触れずして、今の音楽は語れないというところまで来ています。先日BS世界のドキュメンタリーで放送された「サウンドハンター」でその辺の話が詳しく触れられていました。3/21に再放送もされるようなので、オススメです。
ブラジルを代表する作曲家、編曲家、マルチプレイヤー、エルメート・パスコアル(今年の1月に来日もしました)のこの曲「Feira de Asakusa」はサンプリング手法を採り入れた楽曲の最も有名な例の一つです。
浅草の叩き売りの声が、あっと言う間に音楽に変わります!彼のこの手法をさらに洗練させたフランスのChassol(シャソール)も必聴です
さて、このサンプリングというやり方を使ってリンゴの音が大フューチャーされた曲があります。イギリス出身のディープハウスDJ、電子音楽の作曲家マシュー・ハーバートが制作した「In Eating」という作品です。マシューは多くの革新的な作品をリリースしてきた、現代の音楽シーンを代表するような音楽家のひとりなのですが、この曲は彼のキャリアの中でもとりわけ問題作と言われている『ア・ヌード(ザ・パーフェクト・ボディ)』に収録されています。このアルバムは、人間が一日の生活で生む生活音だけを使って制作されたという、サンプリングの極致のような作品。そしてこの「In Eating」ではリンゴを食べはじめて食べ終わるまでの音がテーマになっています。では聴いてください。百文は一聴にしかず。
人が一日の暮らしの中でたてる音には本当にたくさんの種類がありますが、その中からわざわざリンゴが選ばれたということに、何か特別な意味がありそうです。現代最高の作曲家のマシューがセレクトしたリンゴは「世界で最も音楽的な果物」と言っても良いのかもしれません。そのうち、かじる音だけじゃなくて、叩く音などリンゴの音だけを使ったサンプリング・アルバムも生まれるのかも。私たちは、リンゴをかじる時、音楽を聴いているんですね。最後に疑問を一つ。農家の人は、リンゴをかじる音だけ聴いて品種がわかるものなんでしょうか? いつかリンゴ農家さんに訊いてみたいと思っています。
2017/3/9
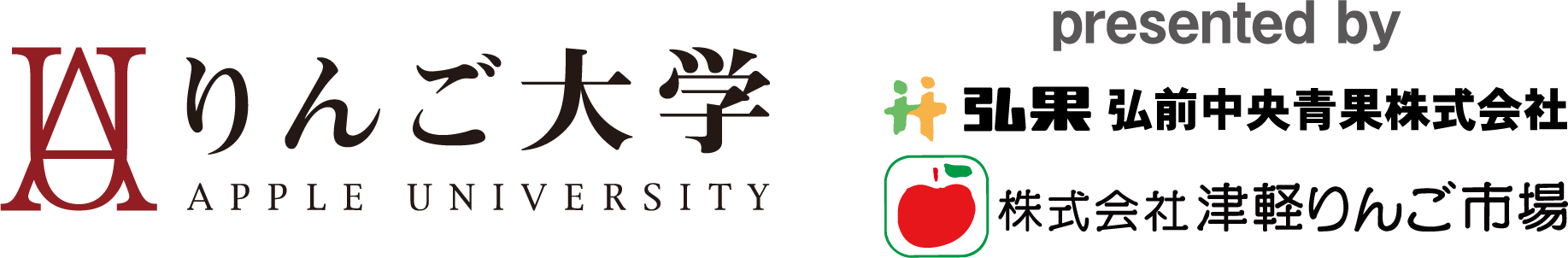

 繁体中文
繁体中文 簡体中文
簡体中文 English
English




