vol.20 リンゴとは、遠きにありて想うもの
大阪出身なのでよく言われるのです、「大阪って面白いところですよね」と。そして「あんな面白くて、ご飯も安くておいしい街で育って、いいなあ」という言葉が続きます。うーん、実はその言葉、少々微妙な気持ちで聴いているんです。実は私、大阪に全くと言っていいほど愛着がないんです。はっきり言ってしまうと、好きではない。それも、かなり「嫌い」に近い、好きではない、です。
私の両親はいま大阪の堺市に住んでいるのですが、もし親が他県に引っ越してしまったら、私が大阪に帰る理由は失われると思います。少なくとも、積極的に足を運ぶことはもうないでしょう。というわけで、大阪に対してあまり「ふるさと」という感情を持っていないんです。私のように、実際のふるさとがそんなに好きではないという人は、あまりいないことにされていますが、実は一定数存在していて、そういう人たちはざっくりと「愛郷心のない人」とか「ふるさとを捨てた人」というふうに分類されます。
しかしほんとうにそうなのでしょうか。私たちのような人間には「ふるさとを思う心」はまったく存在しないのでしょうか。青森市に引っ越してきてから10数年経ち、いつもそんなことを考えています。というのも、先日こんなことがあったからです。
7月の上旬から下旬にかけて、17日間のヨーロッパ取材に行ってきました。デンマーク、ハンガリー、スロヴァキア、ポーランドの4ヵ国が訪問先でした。海外取材などと書くと、みなさんは私のことを英語や外国語が堪能だと思うかもしれませんが、実は英語は独学で習得状況は亀の歩み。メールなど文章でやりとりするのはそれなりに上達したのですが、会話はまだまだなんです。当然、その他の言語などほぼまったくできません。

また、私のような単身取材者には、テレビの撮影のように通訳さんがついてきたりはしません。基本的にすべて自分で交渉したり、インタビューしたりします。撮影クルーなんかもいないので、フォトグラファーも自分自身です。知らない街を訪ねたり、普段はフェイスブックなどでやりとりしているだけのミュージシャンたちに実際に会えるのはとても楽しい体験です。しかし一方で、英語力に不安を抱える自分にとって、外国への取材旅行は相当なプレッシャーをともないます。そして、疲労が重なると集中力も落ち、英語が全然聞き取れないし、話せなくなってきます。

今回の取材旅の最後の訪問国はポーランドでした。デンマークの首都コペンハーゲンに降り立ってから10日以上経ち、だんだん英語の会話にも慣れ始めているのと同時に、旅の疲れも溜まってきてもいました。おまけに、その時私が参加していたのは、エジプト、インドネシア、中国、イギリス、クロアチアなどなど世界各国の音楽関係者が呼ばれて一緒にいろんなコンサートを見るというもので、朝起きてから夜寝るまでの間、つねに誰かと喋っていないといけないような環境でした。しかも当然、みんなは英語が堪能です。

そんな毎日の中で、私がほっと一息つける時がありました。ライヴ会場には軽食のケータリング・サービスがあって、お茶やお菓子、パンなどいろんなものが置いてあったのですが、その中にアップルティーやペットボトルのリンゴジュースもあったのです。なぜかと言うと、ポーランドは世界で五本の指に入るリンゴ生産国だからです。会場のスタッフに「何にします?」と訊かれた時、私は必ずリンゴがらみのドリンクやお菓子を選んで、食べたり飲んだりしながら青森のことを思い出し、少しリラックスできたのです。ちょっと舌も滑らかになって、「僕の住んでいる街は東京ではなく青森と言うところで、すごく雪が降って、このポーランドと同じでリンゴがたくさん採れて・・・」などとみんなに向けて青森PRもしたりしました。

これは一種の愛郷心ではないのかな、と私は思うのです。「ふるさと」とは、一般的に生まれ育った街のことを指します。でも、遠く離れた場所で、今住んでいる街、あるいは前に長く住んでいた街に深く関係するものに触れた時、わけもなく安心する、緊張が解けるということもあるのではないでしょうか。もしそういう時間が訪れた時、その街は、その人にとって一種のふるさとになったのです。

ところで、ポーランドには大作曲家ショパンがいます。全盛期の作品のほとんどを亡命先のフランスで作曲したため、ポーランド人であるということを知らない人も多いかもしれません。が、彼の心臓は死後ワルシャワに埋葬され、今もこの国の象徴として尊敬されています。ポーランド人は、歴史に対して非常にセンシティヴな感性を持っています。第二次大戦中のドイツ軍の空爆で更地になるまで破壊し尽くされたワルシャワの街を、住民の記憶に従って、ひびの一つにいたるまで可能な限り「元の形」に戻したエピソードなど、その最たるものでしょう。また、DVD売り場に行くと、普通の映画と同じくらい広さで、ドキュメンタリーのためにスペースを割いています。歴史と、その記録と記憶を未来に引き継ぐことに本気の国民性の表れでしょう。

とは言え、今も昔も、また世界中のどこでも、若者の伝統軽視はあります。ポーランド人でも「今さらショパンかよ」「ショパンなんてダサいよ」と言う若い人も当然います。また、ポーランドではショパンの曲を演奏したクラシックのCDや、ジャズやポップスとしてカヴァーしたものが毎年たくさん発売されます。そんな中、天邪鬼な性格の人なら、きっと「もうショパンはいいよ!」と感じるはず。私もかなりのはねっかえりなので、ポーランド人だったらきっとそういう人になっていたに違いありません。
ショパンのジャズ・カヴァーで一番好きなアルバムのひとつ。
友人のピアニスト、クバ・スタンキェヴィチがショパンの19の歌曲集を女性ヴォーカル・ジャズとしてアレンジしたものです
でも一方で、ポーランド国外に住むポーランド人からはこんな声も聞かれます。「ポーランドにいた時は、ショパンなんて何とも思ってなかったけれど、離れている今ならわかる。彼の音楽は、僕たちのふるさとなんだと」。そんな彼ら彼女らの感想を、ポーランド人ではない私は「ふーん、そんなもんかあ」とわかったようなわからないような気持ちで聞いていたのですが、そんな私も今ならわかります。緊張と疲労が重なり、エンドレスに続く英語での会話にへばっていた私を安堵させたリンゴの味の、あの感じなんだと。だから青森は今、私の「ふるさと」なんです。

2018/9/1
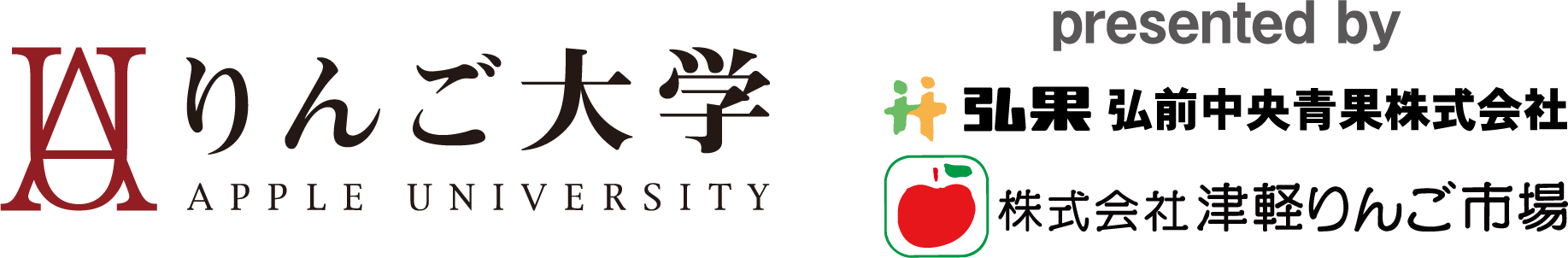

 繁体中文
繁体中文 簡体中文
簡体中文 English
English




