vol.10 摘果とボツ・テイク
音楽を楽しむという行いは、メディアと技術の進化によってそのかたちがどんどん変わってきています。はるか昔は「録音する」ことができませんでしたから、当然「音楽を聴くイコール生演奏に接する」でした。そして個人的に一番大きな変化だったなと思っているのがレコードからCDへの変化です。それは、だいたい80年代の半ばくらいに起こりました。年齢的に、ちょうど思春期に入る辺りにその変化を目の当たりにしましたから、その意味でも思い入れが深いのかも知れません。
CDという媒体が誕生日を迎える前のエピソードで、こんなものがあります。オーストリア出身の大指揮者ヘルベルト・フォン・カラヤンが、当時CDを開発中だったフィリップス社から収録時間について意見を訊かれたのだそうです。その時彼は「ベートーベンの交響曲第9番<合唱>がまるまる一曲入る長さくらいがいい」と答えたそうです。その後紆余曲折あって、CDの標準規格は74分ということに決まり、リリースが開始されました。
カラヤンの「第九」。77年のニュー・イヤーズ・イヴ・コンサートです
実際はフィリップスはカラヤンの希望とは違う規格を採用しようとしていたそうですが、今の時代に例えるならApple Musicの開発でクラシックの指揮者や演奏家に意見を求めるようなものでしょうか。フィリップスがクラシック中心のレーベルだったということもありますが、今では数千枚売れれば大ベストセラーと言われるクラシックにおいて、当時数百万枚のセールスを記録していたカラヤンの、世の中における影響力の凄まじさを物語るお話です。余談ですが、昔ワールドミュージックのショップで購入した東南アジアや中近東のCDには無理矢理80分くらい収録しているCDもあって、プレイヤーによっては再生できない場合もありました。74分はあくまで「世界標準規格」で、もっとゆるいノリの国もあるということです。
さて、それまでレコードで聴いていた音楽リスナーの世界にCDがやって来てどういうことが起こったか。大学の卒論で、60年代以降の日本人のコミュニケーションとアイデンティティのあり方と、メディアと音楽の変遷はそれぞれつながっているみたいな説を書いたのですが、音楽がデジタル・データ化され利便化されると、ラジオやレコードを「家族や他の人もいる空間」で楽しむという「音楽を共有する環境」がなくなり、どんどん「自分一人のもの」になっていきます。デジタル化によって発展したカラオケも、ちゃんとした音響設備のもとで歌うという行為を個人所有化したものだと言えます。道理で、数人でカラオケに行っても自分の曲選びに忙しく、基本誰も人の歌を聴いていませんもんね(笑)
まあ小難しい話はこれくらいにしておいて、CD時代の到来でもうひとつ変わったことがあります。それはいわゆる「ボツ・テイク」の併録です。外国の作品だとAltanate TakeとかPreviously Unreleasedとか書いてあるあれです。特に過去にレコードでリリースされていたジャズのアルバムに顕著な現象です。ジャズはアドリブ(即興、インプロヴィゼイション)の上に成り立っている音楽なので、数十年前はみんなで「せーの」で一緒に演奏してそれをそのまま録音する「一発録り」という方式が当たり前でした。そのかわりしっくりこない場合は何度も同じ曲を録音していたわけです。そうした試行錯誤を経て、レコードに演奏者みんなが納得するテイクだけが収録されていたのです。70年代には演奏と同時にその音をレコードの溝に刻み込む「ダイレクト・カッティング」という方式も流行りました。このやり方だと、片面分録音をやり切るまで演奏を途中でやめることすらできません。
ジャズ・ギタリスト、リー・リトナーのダイレクト・カッティング方式による名演がこちら
レコードの場合、収録時間が短いので基本的にボツ・テイクを収録するスペースはありません。でもCDがメインになると、収録時間も余裕があるし、スイッチ一つでかんたんに曲を飛ばせるので、そうした未発表録音も入れてリリースするのが当たり前になりました。ところが、ポップスや他のジャンルではこうしたボツ・テイクの収録は一般的ではありません。ではなぜジャズだけがそうしたやり方に意欲的なのでしょうか。
ジャズは瞬間作曲のようなものなので、メロディを弾き損じたなど明らかなミスでなくてもボツになるパターンも多いのですね。判断基準はミュージシャン本人やプロデューサーの「これはいい演奏かどうか」という感覚だけと言ってもいいでしょう。なので、本テイクとして採用されなかったものでも聴く価値があるし、面白いんです。ボツと判断されたものをわざわざ収録することに関してはもちろん賛否両論があります。批判の代表的なものは、アルバムの流れを損ねるとかアーティスト側の意向を無視しているというものでしょうか。ですが、聴き比べることで勉強や研究になることもまた、事実です。
ジャズの帝王マイルス・デイヴィスの問題作「イン・ア・サイレント・ウェイ」から。プロデューサーのテオ・マセロがマイルス・バンドがスタジオでセッションした音源テープに鋏を入れまくって作り上げたものです。ボックスCDセット「ザ・コンプリート・イン・ア・サイレント・ウェイ・セッションズ」で編集前の音源が聴けるようになり、マセロの天才を多くの人が再発見しました。これもまたCD時代の賜物です
こうしたボツ・テイク収録で改めて浮き彫りになったことがあります。それは、ジャズのようなある種行き当たりばったり、一発勝負なジャンルですら、レコードという商品になる際は選び抜かれたものが提供されているということです。私はこれ、リンゴの栽培と同じだなと感じました。自分の身の周りにリンゴ農家さんがいないとなかなかわからないことですが、リンゴはただ育ったものの中からいいものだけを選んで売っているのではなくて、いいものが育つように何段階もの選定作業を経ているのです。いい実が育つのは偶然ではなくて必然なのです。もう少し具体的に説明しましょう。
リンゴの木はそのまま実を放置していると、一枝につき、いくつもの小さな実が育つだけです。それぞれの実に木の栄養が均等に行き渡ってしまうので、そのままでは私たちが知っているようなあの大きな実は育ちません。そこで「摘果(てきか)」や「すぐり」と呼ばれる作業で枝の根元に近い実を残して、他の実は取り払ってしまいます。そうすることで、その実にだけ栄養が注がれるようになります。この作業は何度も行われます。時間をおいて、残した実がどんな風に育つのか農家さんは見ています。また、葉っぱの栄養が実が育つためにとても大事なので、機が熟すまで葉っぱも残しておき、タイミングが来たら今度は日光がたっぷりと実に当たるように葉っぱを取り除く作業も行われます。ざっとした説明ですが、このように気が遠くなるほどの手間をかけてリンゴの実はあの大きさ、美しさに育っているのです。

作り込まれたポップ・ミュージックも、アドリブで瞬間的に作り上げるジャズも、とてつもなく厳しい選別眼と、確実にいいものを育て上げる練習があってはじめて成り立っています。そこに至るまで、ミュージシャンたちはいったいどれほど没テイクを重ねたのでしょう。そんな当たり前のことを、電車の窓からリンゴ畑を眺めるたびに、私は思い出します。
2016/8/23
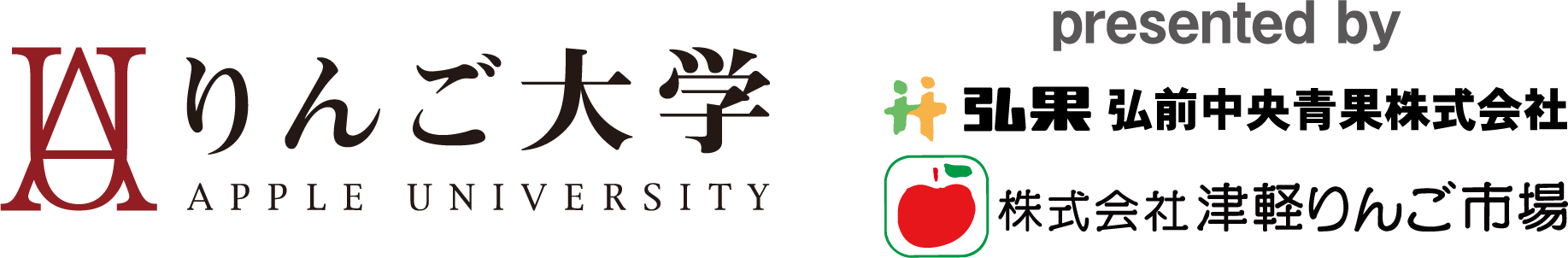

 繁体中文
繁体中文 簡体中文
簡体中文 English
English




