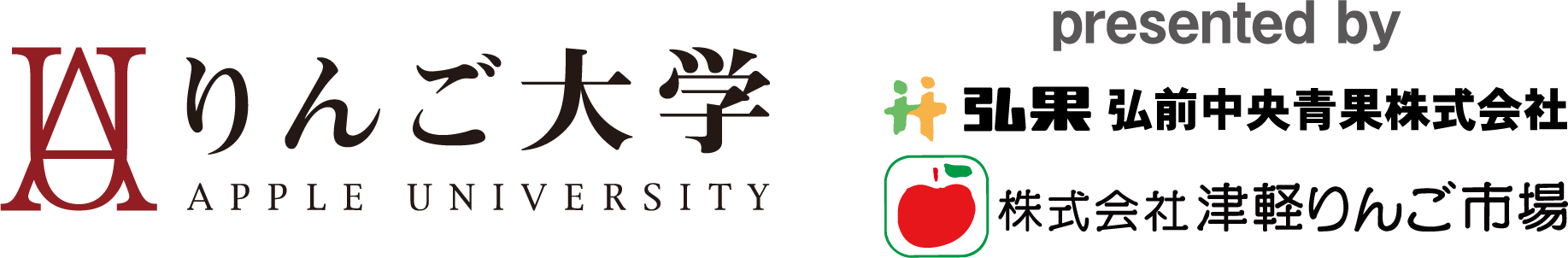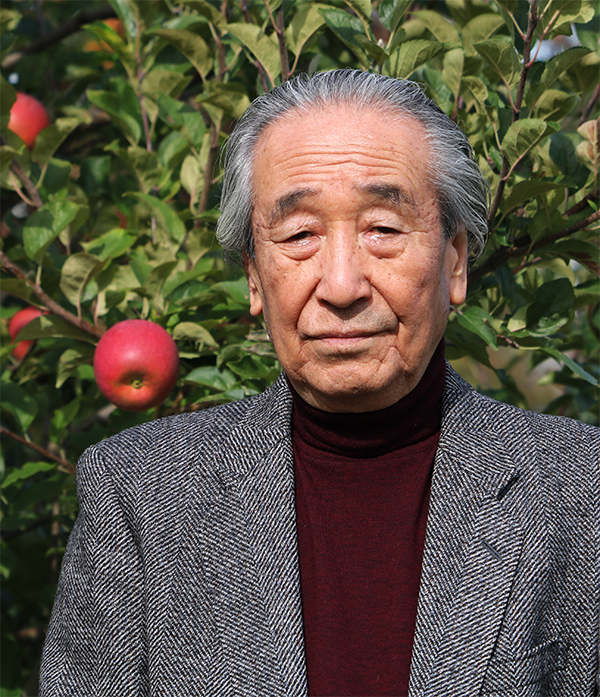第5回 りんご・リンゴ・林檎・苹果
「りんごは、日本語として響きがうつくしい。賞でて発音すると、赤くて果実のはちきれそうな感じがする。」
司馬遼太郎が書いた青森県の紀行文「街道をゆく41、北のまほろば」(朝日新聞社)最終章「リンゴの涙」に出てくる一節である。
平仮名の「りんご」は行政用語などに、片仮名の「リンゴ」は植物用語、新聞用語として用いられるが、人それぞれの好みもある。
リンゴの漢字は、一般的に「林檎」と表記する。昔の八百屋の店先きなどには、「林子」と書いてある札を見たことがある。難しく言えば、「林檎」は中国北部原産の渡来品である。わが国では和林檎(ワリンゴ)あるいは地林檎(ジリンゴ)と呼ばれているものである。

「林檎」という漢字は、昔の中国の書物に見られる。
平安中期の日本初の漢和辞典「源 順:和名抄」には「林檎」を万葉仮名で「利宇古宇(リウコウ)」と読ませている。
「リウコウ」から次第に「リンキン」、「リンゴ」のように移っていったようである。
この時代の辞典は、中国の書物に出てくる名と物との対訳に専念したものであり、「林檎」の実物がこの時代に渡来していたかどうかは明らかでない。
奈良時代から江戸時代までの種々の書物を見ると、10世紀後半から11世紀後半にかけて半分色づく果実をつける「林檎」が、17世紀前半にはやや縦長の赤い果実をつける「林檎」の変種である「リンキン」または「リンキ」が、中国大陸や朝鮮との交易によって日本海沿岸に渡来したものと考えられる。
日常の果実として、「林檎」の名が現れるのは鎌倉時代中期頃からで、平安時代に渡来していなかったか、あるいは渡来していても栽培はまれであったと思われる。鎌倉時代以降の古典や古文書には、「林檎」は上流社会の贈答品あるいは献上品として珍重されている。
江戸時代に入ると、「林檎」の栽培は九州から東北地方までの限られた地域に広がっていった。京都の名産として嵯峨および大宮の「林檎」が上げられている。ナシ、カキ、ウメ、スモモ、モモに比べると「林檎」の生産量は少なく、人気のある果物ではなかった。
これらの「林檎」は横径3.5~4cm、縦径3.0~3.5㎝と小さいが、赤く色がつき微酸性で甘味もある。収穫期は7月下旬~8月下旬で、貯蔵性は低い。熟期がお盆と重なるため、供え物として大事なものであった。この風習は日本の各地で行われていた。
明治時代に政府は果樹殖産政策により、欧米から大量の「セイヨウリンゴ」苗木が導入され全国に配布された。美味しく大きな果実の「セイヨウリンゴ」の栽培が拡大するにつれて、「林檎」の栽培は激減する。
当初、「セイヨウリンゴ」に「林檎」の和名をつけたが、在来種の「林檎」と区別するために、1876年に「苹果(ヘイカ)」とした。中国では古くから食用として栽培されていた大形の「林檎」を苹果と表記していたからである。

「苹果」は明治の前半から昭和の前半まで公の文書には普通に使われていた。
1931年に全国初のリンゴに関する専門試験場として青森県農事試験から独立したときの名称は青森県苹果試験場であった。1950年に青森県りんご試験場に名称を変更した。その後「苹果」の漢字表記は、ほとんど使われなくなった。
「林檎」が「ワリンゴ・ジリンゴ」を意味するという区別は一般的でなくなり、「苹果」が日本語であったことも忘れられている。
1950年代の後半まで、黒石市の人々は地元のりんご試験場を「ヘイカ試験場」と呼ぶ人が結構多くいた。りんご試験場には、昭和天皇が3回も行幸されたことから「ヘイカ試験場」と言うのかと、真面目に言った人もいた。
「ワリンゴ」、「ジリンゴ」と呼ばれる在来林檎は、「高坂りんご(長野県飯綱町)」、「彦根りんご(滋賀県彦根市)」、「おおわに和りんご(青森県大鰐町)」など全国11か所に現存している。
関係者は江戸時代から受け継がれている遺産とも言うべき「林檎」を次代に残そうと懸命な努力を続けている。
(2018/4/17)