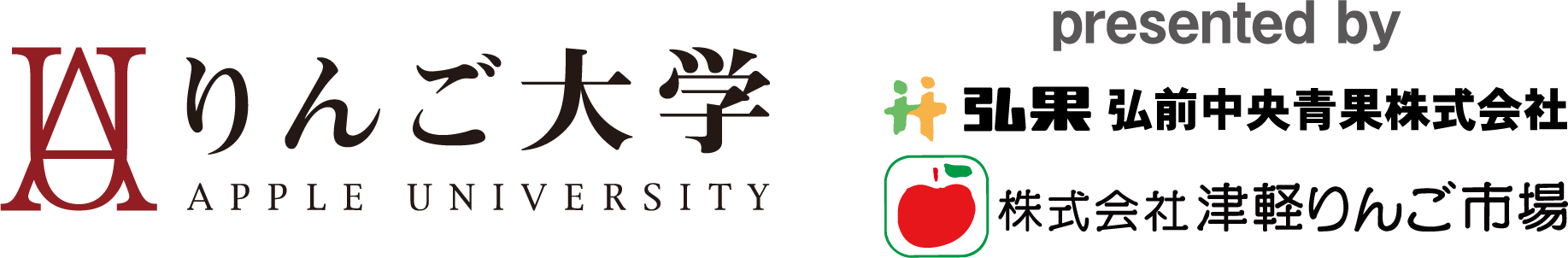Vol.3 バカンスとシードルは甘くない

大きな鞄に荷物をたっぷり詰め込んで、友達と、恋人と、田舎町へのんびり遊びに行く。山でピクニックをしてもいいし、海で日光浴をしたり、家のなかでひたすら読書を楽しんだっていい。とにかく仕事や勉強のことは忘れて2、3週間、ただ飲んで食べて寝て、をくりかえす。最高に楽しくてすてきな、あこがれの、夏のバカンス。
そんなバカンスへのイメージがどうやら幻想にすぎないらしい、と気づいたのは、フランス映画を見始めたからだ。映画の中で見るバカンスは必ずしも楽しそうではなく、もっと殺伐として、いろんなもめ事に満ちていた。どうも夢のような光景とは違うぞ、と気づき始め、エリック・ロメールの『緑の光線』(1985年)を見て、ついにその思いは決定的になった。『緑の光線』の主人公は、パリで働く若い女性デルフィーヌ。恋人がおらず、寂しがりな彼女がバカンスを通じて幸福をつかめるか? という物語は一応ある。ラストでは映画史に残るすばらしいシーンも用意されている。それにも関わらず、映画を見たときの率直な印象は「バカンスはつらいよ物語」だった。
一緒にバカンスへ行くはずだった友達にドタキャンされ、困った彼女は、別の友人の誘いで南仏へ出かけるが、見知らぬ人々に囲まれてまったくその場になじめない。一旦パリへ戻ったあと、今度はひとりで山へ出かけてみたり、また別の海辺へ出かけてみたりするけれど、どこへ行っても孤独感は薄まらない。いっそのことひとりで平然と過ごせばいいのに、と思うが、寂しがりな彼女にはそれが耐えられない。かといって、誰かその場で相手を見つけるには、シャイすぎる。
「私には誰もいない。友達にはバカンスを断られるし、どこへ行ってもなじめない」とめそめそ泣くデルフィーヌを見ていると、バカンスに抱いていた理想がガラガラと崩れていく。映画が極端なのかもしれないが、相手がいないバカンスはたしかに寂しい。とはいえ、観光をするでもなく何日も同じ場所で一緒に過ごしていたら、友だちだろうが、家族だろうが、そのうち嫌気がさしてくるのも当然だ。
「バカンスつらいよ物語」といえば、ジャック・ロジエの『オルエットの方へ』(1971年)も忘れられない。こちらもパリで働く女の子たちが、海辺の別荘でバカンスを過ごす物語。『緑の光線』とは違い、女の子3人でのバカンスは、笑いとバカ騒ぎに満ちている。ここで寂しい思いをするのは、彼女たちのうちの一人を追ってやってきた、会社の上司ジルベール。気になる子を口説きたくて、偶然のふりをして追いかけてきたものの、その魂胆を見抜いた女の子たちに振り回され、彼のバカンスは散々なものになる。ジルベールへの仕打ちはまあ当然だけれど、張り切って料理をつくってもろくに食べてもらえず追い出されるのは、さすがに可哀想。結局、ジルベールは失意のなかパリへ帰ってしまう。その後も彼女たちのバカンスは続くが、この一件が尾を引いて、なんとなく雰囲気がギスギスしてくる。ある朝、別荘の冷蔵庫が空っぽだと気づいた女の子たちは、朝ご飯を食べに別荘の下のカフェへ顔を出す。注文したのはワッフルとシードル。雰囲気の悪さを吹き飛ばすように、「まずはシードルでも飲もうよ!」とひとりが瓶の蓋を景気よく開けてみせる。朝からお酒なんて、と思うけれど、シードルならたいして気にならないのが不思議といえば不思議だ。
そういえば、フランスに初めて行ったとき、ガレット屋で飲んだシードルに驚いた覚えがある。シードルといえば、なんとなく、りんごジュースのアルコール版というイメージがあって、甘ったるいお酒だと思っていた。でもそこで飲んだシードルはピリリと辛口で、思っていたよりもずっと大人の味だった。甘口のシードルもあるけれど、一見可愛らしく見えるからよけいに、その苦さが強烈だった。
シードルが思ったより甘くないように、バカンスもそれほど甘くない。それでも、バカンスを満喫した女たちは、苦々しい経験も、バカな男たちもやりすごして、夏の終わりとともにパリへ戻っていく。朝からワインはやりすぎだけど、シードルなら大丈夫。そう教えてくれたのも、やっぱり映画だった。

本体価格:¥4,800+税
DVD発売中!
販売・発売元:紀伊國屋書店
2019/2/28