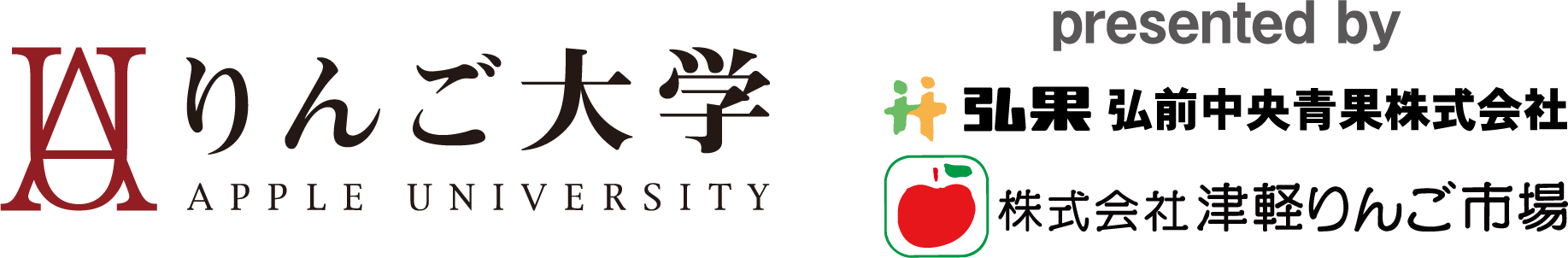Vol.16 笠智衆はりんごの皮を剥く

■映画を見直してみてわかること
最近、過去に見た映画を見直すことが増えてきた。というより、昔見たはずの映画が思い出せなくなってきた。それで、映画について書いたり考えたりする際に、もう一度DVDや配信で、あるいは名画座で見直さざるを得ないのだ。再見するとわかるのは、過去の記憶はまるで役に立たないということ。こういう映画だったよね、という自分の記憶はたいてい間違っていて、いったい何を見ていたのかと我ながら呆れてしまう。
記憶違いだけではない。たしかに覚えがあるシーンや物語なのに、過去に見たときとはまったく別の見え方ができる場合もある。悲しい場面だと思っていたのに、改めて見るととても楽しい場面に感じたり。逆に、軽いコメディのはずが、こんなに寂しい話だったのかと驚いたりもする。映画は、見たときの自分の年齢や環境、気分によって変わってしまう。嫌いな映画を好きになることもあれば、大好きだったはずなのに今は全然心が動かない、なんてこともある。
私が数年前に見直してみて、がらっと感想が変わった映画は、小津安二郎監督の『東京物語』(1953年)。初めて見たのは大学生のとき。夏、広島の尾道からはるばる東京へ遊びに来た老夫婦。東京に住む子供たちを訪ねるのが旅の目的だったはずが、子供たちはみな忙しく、邪険にされてしまう。戸惑う二人を優しく歓待してくれたのは、原節子演じる亡き次男の妻だけ。やがて母が突然亡くなり、子供たちは慌てて葬式に集まるが、ここでも長男や長女はさっさと遺産の話を始めたりする。残された父は、寂しげに子供たちの様子を見つめている。
実をいうと、最初はこの映画を好きにはなれなかった。老夫婦が実の子たちに冷たくされ、本当に優しいのは他人である義理の娘だけ、なんてなんだか教訓話みたい、と思った。だけど久々に見直すと、これが全然違う映画に見えた。自分が歳をとったからなのか、描かれる出来事がどれも身近に感じられ、出てくる人たちみんなに親近感が湧いてきた。身勝手で冷たいと思っていた子供たちだって、みな自分の仕事や家族のことで手一杯なだけ。母親が危篤状態に陥っても涙ひとつ流さず、「一応喪服も持って行こうか。使わなきゃ使わないでいいんだからさ」なんて言ってのける杉村春子演じる長女だって、昔見たときには「なんて薄情な人」と思えたけれど、今では「まあそういうこともあるよね。葬式の心の準備だって必要だし」としんみりしてしまう。
感想ががらりと変わったのは、きっと自分がこの子供たちの年齢に近くなったからだ。数十年後、この両親の年代になれば、また別の見方ができるかもしれない。
■父と娘の物語『晩春』
小津の映画でもうひとつ、実は苦手に思っていた作品がある。それは、1949年に撮られた『晩春』。小津安二郎が初めて原節子を起用した記念碑的作品。また脚本家、野田高悟と初めてコンビを組んだ映画でもある。『晩春』は、北鎌倉に暮らす大学教授の父周吉(笠智衆)と、その娘紀子(原節子)の物語。母を亡くして以来、父とふたりきりで暮らす紀子を心配し、周囲はしきりに結婚を勧めるが、本人にその気はない。最初はのんきに構えていた周吉も、妹にうるさく言われるうち、このまま結婚せずにいたらどうなるか、と娘が心配になってくる。仕方なく、「自分も再婚を考えているから、お前も早く結婚して家を出ていったほうがいい」と噓をつき、紀子に見合いを勧める。
紀子は、戦時中、栄養不足から体を壊していたらしいが、今ではすっかり元気になり、毎日楽しく過ごしている。北鎌倉での父との二人暮らしには心から満足しているようだ。彼女は、妻を亡くしてから仕事一筋で生きる父を敬愛している。やはり妻を亡くした父の友人が最近再婚したのを聞くと、「不潔よ」「汚らしいわ」と言い放ち、自分の父は絶対にそんなことはしない、と信じて疑わない。だからこそ、父も再婚を考えているらしいと知ると、激しく動揺し、家から飛び出してしまう。
結婚を渋る娘と、噓をついてまで娘に結婚をさせる父。この物語は、小津監督の遺作となった『秋刀魚の味』(1962年)にも引き継がれる。ここでは娘の結婚を心配する父を笠智衆が、娘役は岩下志麻が演じている。『秋日和』(1960年)では、これを母と娘に置き換えてやはり同じ物語が語られる。夫を亡くし、ひとりで娘を育ててきた母親を演じるのは原節子。司葉子演じる娘に結婚をさせるため、母は再婚をほのめかし、娘はそんな母に失望と怒りを感じながらも、新生活へと一歩踏み出していく。
■結婚を急かされる原節子に感じていたこと
なぜ『晩春』が苦手だったのかといえば、理由はふたつ。ひとつは、紀子が父親を慕い、固執する様が少し不気味に思えたから。見合いをした後も「私はお父さんとずっと二人で暮らしたいんです」と涙ながらに訴えたり、父の再婚相手(実は勘違いなのだけれど)を嫉妬に満ちた目で睨みつけたり、どうしてこれほど父親に執着するのかよくわからなかった。
もうひとつは、紀子が盛んに結婚を急かされる様子に辟易してしまったせい。舞台は戦後間もない日本。女性はみな結婚し、主婦、そして母になるのが当然だと思われていた時代。20代半ばの紀子は、職業婦人でもなく、家で父親の世話をしているだけ。まわりが心配するのも当然といえば当然だが、それにしても、本人にその気がないのに「とにかく結婚しさえすれば」とか「もういいかげん(嫁に)行かせなきゃ」とか周囲は勝手なおせっかいばかり。これでは紀子が物扱いじゃないかと、見ていてイライラした。
けれど久方ぶりに見直してみると、こちらもずいぶんと見え方が変わっていた。物語自体は同じなのに、以前は目に入らなかったいろんな細部に惹かれた。たとえば同級生で親友同士の紀子とアヤの関係。アヤは、一度恋愛結婚をしたものの離婚をし、今は仕事をしながら東京で暮らしている女性。アヤといるときの紀子は子供みたいだ。家にアヤが来たと知ると、大喜びで彼女を迎え、早く早くと、自室のある二階へ引っ張っていく。いつもは「おい、お茶」なんて威張って命じている父・周吉も、その潑剌さに気圧される。二人をもてなそうと、慣れないティーセットを用意しておそるおそる二階へ上がってくる様が妙におかしい。
アヤは、紀子相手に言いたい放題。父や叔母と同じように、なぜさっさと(お嫁に)行かないのかと紀子をけしかける。ただし二人のやりとりはもっとさっぱりしている。「いつ行くのよ、あんた」「行かないわよ」「行っちゃいなさいよ早く」「いやよ」「行っちゃえ行っちゃえ」と笑顔でやりあい、しまいには、離婚歴があるアヤに紀子が「出戻り!」なんて悪態をつく。アヤの方は、自分はまだワン・アウトでこれから大ヒットを打つ予定だと澄ました顔で答えてみせる。仲がいいからこその軽口はただただ楽しくて、紀子はこんなにもユーモアのある人だったのだと初めて気がついた。
■幸福を求めて抵抗した娘と、無言でりんごを剥く父
そんなふうにこの物語を見直すと、いろんな場面が新鮮に思えてくる。なぜ紀子がこれほど結婚を嫌がっていたのか、その理由も、以前とは違う捉え方をしたくなる。父への執着と思われた意固地さは、もしかすると、今の生活への愛着だったのかもしれない。紀子はいわゆる「家事手伝い」という立場だが、日々、充実した生活を送る自立した女性でもある。父が書いた原稿を清書し、必要なものがあれば買い物へ行き、家では料理から客の相手までなんでもする。時々は友達と遊んだり、美術館やコンサートに出かけたりもする。そんな生活を、紀子は愛している。仕事をし、友人と遊び、自分の時間をもつ。そうしたすべてを彼女は慈しみ、手放したくないと願う。いつか父親が亡くなっても、きっと彼女は、ひとりでこの家でのびのびと暮らしていくだろう。
紀子の結婚への拒否反応は、今の幸福を奪われることへの抵抗だ。なぜこの満ち足りた暮らしを捨て、見知らぬ男のもとに嫁がなければいけないのか。その問いに、誰も答えてはくれない。結婚をするのが普通だから。女は夫を持ち、子供をつくるべきだから。実家で生涯独身のまま暮らすなんて、よっぽどの事情がなければ許されない。そんな「普通」の感覚に、紀子は異議を申し立てる。でも結局、彼女は唯一の味方である父に裏切られ、降参し、この家から出ていかざるをえなくなる。
これは父と娘の愛を描いた物語ではなく、若い女が自分の生活を守るため戦おうとする話だったのだ。彼女は戦いに敗れてしまうけれど、最後まで精一杯の抵抗をし、結婚が本当に幸福と言えるのか、と私たちに疑問を投げかける。こんなふうに別の角度から眺めてみたら、苦手だと思った『晩春』という映画が断然好きになった。快活に笑い、怒り、ぽんぽんと言いたいことを言う原節子は、前よりずっと素敵に見えた。
映画は、原節子ではなく、父親役の笠智衆ひとりを映して幕を閉じる。娘の結婚式を終え、周吉はひとり北鎌倉の家へ帰ってくる。静かになった家のなかで、居間の椅子に座ると彼は小さなりんごを持ち、ナイフで皮を剥き始める。そろりそろりと皮を剥くうち、彼の瞳には涙がにじんでくる。愛する娘を手放し、これからはひとりで生きていくのだと、寂しさを嚙み締めているのだろうか。あるいは、強引に娘を結婚させ、家から追い出したことへの後悔かもしれない。娘の好きに生きさせる道だってあったはずなのに。できればそんな悔いを抱えていてほしいと、私はつい願ってしまう。
ラストシーン。言葉は何ひとつ発せられない。ただ黙ってりんごを剥く老人を映し、この物語は終わりを告げる。

好評発売中
Blu-ray:5,170円(税込)
発売・販売元:松竹
Ⓒ1949/2015松竹株式会社
2021/4/30