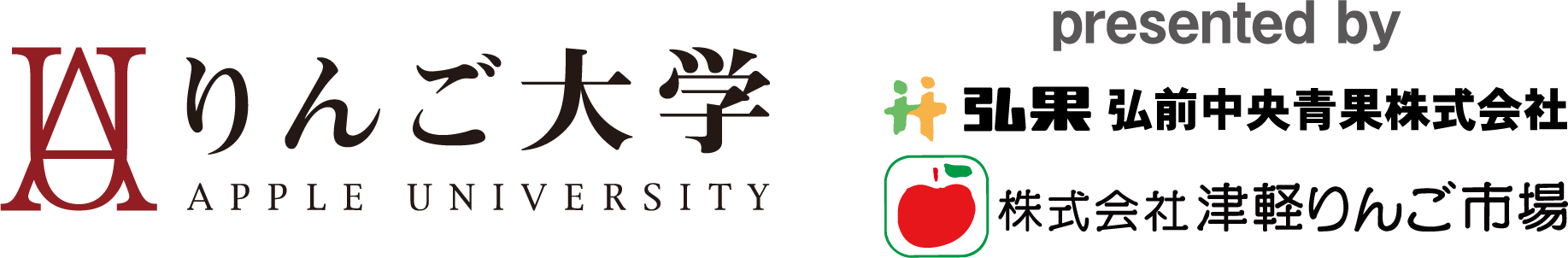Vol.17 りんごに囲まれて育った少女の青春物語

■内気な少女の青春物語『いとみち』
たどたどしく言葉を吐き出す少女。重たい口を必死で開こうとするけれど、うまく言葉が出てこない。どんなに「普通」にしゃべろうとしても、強い訛りがまつわりついて、それがよけいに口を重くする。しゃべりたいことがないわけではないし、むしろ頭のなかにはいろんな言葉が溢れている。だけどそれらをうまくまとめることができない。頭のなかと体の動きがどうにも一致しない。だからまずは体を動かすことから始めようと彼女は決意する。これはそんな少女の物語。
青森出身の横浜聡子監督の最新作『いとみち』は、青森県板柳町で暮らす高校生、相馬いと(駒井蓮)を主人公にした青春物語。幼い頃に母を亡くし、津軽三味線の名手である祖母(西山洋子)と大学教授の父(豊川悦司)と3人で暮らしてきたいとは、祖母譲りの強い津軽弁が消えず、学校ではどこか浮いた存在。決して疎まれているわけではないが、生来の人見知りのせいもあり、うまく友達をつくれずにいる。いとの父は東京出身だが、板柳出身の母と結婚しこの地に来て以来、すっかりここが気に入った様子。今は大学で民俗学を教え、学生と一緒に津軽弁の研究をしているようだ。
いとは、家でも自分の居場所を探している。祖母や母の影響でかつては津軽三味線に夢中になっていたが、今ではすっかり弾かなくなり、そのことを父から諌められる。別に嫌いになったわけじゃない。でも祖母のようにはうまく弾けないという引け目や年頃ゆえの羞恥心が、彼女を三味線から遠ざけてしまう。
ただ退屈をもてあますばかりの毎日、そんなある日、いとは青森市のメイドカフェでバイトを募集していることを知り、興味を抱く。惹かれた理由は、可愛らしいメイド服か、もしくは日常からもっとも離れた場所に行きたかったのか。はるばる青森市まで電車を乗り継ぎ、メイドカフェ「津軽メイド珈琲店」を訪ねたいとは、個性豊かな店の人々に圧倒されながらも、メイドの一人として働くことに。当初は、津軽弁が抜けず、挨拶すらまともにできずに悩んでいた彼女は、仲間に支えられ徐々に店に馴染んでいく。また学校でも、クラスメイトの早苗(ジョナゴールド)と仲良くなり、いとの日常はゆっくりと変化を遂げていく。だがそんななか「津軽メイド珈琲店」に大きな災難がふりかかる。
■横浜聡子監督が描く青森の風景

この映画を監督した横浜聡子監督は、これまでも青森を舞台にさまざまな映画をつくってきた。冬の青森で撮影した初監督作『ちえみちゃんとこっくんぱっちょ』(2005)から、八戸出身の松山ケンイチが主演した『ウルトラミラクルラブストーリー』(2009)、そして弘前のりんご農家を舞台にした中編『りんごのうかの少女』(2013)。どれも青森を舞台に、一風変わった人々が織りなす物語。どこかファンタジーのような不思議なユーモアに満ちていて、予想もつかない展開に呆気に取られつつ、見ていて夢中になる。見慣れた青森の風景もたっぷりと映され、地元の人たちがしゃべる津軽弁を存分に味わえるのも嬉しい。
にもかかわらず、青森の魅力に溢れた映画か、と言われると少々言葉に詰まる。横浜監督の描く青森は、いつも暴力と狂気が満ち溢れているからだ。そこは閉塞感が漂う陰鬱な場所で、登場人物たちはみな破壊や死へと引き寄せられていく。たとえば『りんごのうかの少女』には広々とした立派なりんご農園が登場するけれど、ここで育った少女りん子にとってそれは憎悪の対象でしかない。この場所を出ていきたい、家族から逃れたいと願う少女は、りんご園を燃やし、人生を一からやり直すことを願っている。
こうした過去作品を見ていたせいか、『いとみち』が描く青森の明るさに、まず驚かされた。りんごの木がずらりと並ぶ板柳町も、いとの高校がある弘前市も、メイドカフェがある青森市も、その風景は私がよく知る身近な場所そのもの。過去作にあった陰鬱さはまったく感じられず、そのあっけらかんとした明るさに、驚くと同時に懐かしさがこみあげた。
これまでの作品からの変化の理由は、『いとみち』が原作小説をもとにしていることが大きいかもしれない。いともまた、『りんごのうかの少女』のりん子と同様に、地方で暮らす思春期の少女にありがちな、鬱屈した思いを抱えてはいる。何もない街に飽き飽きしていて、自分を変えたい、どこか遠くへ出て行きたいと願っている。でも「青森から出て東京へ!」という明確な思いはまだ持っていない。三味線を弾くのはもう嫌だ、と思ってはいるが、二度と弾きたくない、というほど強い拒否感もない。家族はうっとおしいが、口も聞きたくないほど嫌いなわけじゃない。いとの抱える反抗心はもっと曖昧で穏やかだ。何かを変えたい、自分の思いを体から発散させたい、新しいものと出会いたい。でもそれが何なのかがわからない。だからこそ、いとは、自分が何を求めているのかを模索しつづける。
■生活のなかに自然と存在するりんごの姿

板柳町と青森市を舞台にした『いとみち』には、もちろんりんごがたっぷりと登場する。ただし、いかにも、という見せ方にはならない。りんごは、登場人物の生活のなかに自然と存在し続ける。いとが歩く板柳の町では当然のようにりんご園が映り込むし、家の食卓にはいつもさりげなくりんごが載っている。たしか玄関の床には、干し餅や何かと一緒に〈板柳りんごワーク〉のアップルジュースの瓶が置かれていたように思う。りんごはあくまで日常のアイテムで、「さあ青森といえばりんごですよ」とこれ見よがしに出してくることはない。そういえば自分が子供の頃も、りんごは決して特別なものではなく、むしろちょっと飽き飽きするくらい日常のなかに溶け込んでいた。涼しくなれば家にはいつも箱いっぱいのりんごが鎮座していて、好きなときに剥いて食べていた。板柳に住む祖母の家に行けばいつだってりんごジュースを出されたから、たまには別のジュースが飲みたい、なんて思っていた。
一方「津軽メイド珈琲店」は、いとの家とはちょっと違う。店では、従業員の幸子(黒川芽以)がつくるアップルパイが大人気で、店のあちこちにりんごをモチーフにした絵やオブジェが見てとれる。オーナーが東京の流行を取り入れて開いたというわりに、この店では青森特産のりんごを目一杯アピールしている。都会らしさをアピールしたいのか、地元感を強調したいのか。そのちぐはぐさがなんだか可笑しい。でもそういうお店だからこそ、いとは今の自分のまま、堂々と働くことができるのだ。津軽弁訛りの接客を、そのままでいいよ、と呆れつつも受け入れてくれる。どこかいい加減で、でたらめな人ばかりが集まる場所。そこで働くうち、いとはあれほど遠ざけていた三味線を再び手にとることになる。
メイド服と津軽三味線、という飛び道具を使いつつも、物語は一貫して普遍的な青春ストーリーをたどる。内気な少女は、思いがけぬ場所へ飛び込み、いろんな人と出会い、家族と喧嘩し、親友をつくり、やがて自分だけの言葉を獲得する。「自分の言葉」とは、何も口から発せられる言葉だけに限らない。自分の手で、体全体で紡がれるいとの言葉が、映画の最後を力強く彩る。りんごに囲まれて育った少女がこの先どこへ行くのか。そのもっともっと先を見てみたくなった。

ⓒ 2011 越谷オサム/新潮社 ⓒ2021『いとみち』製作委員会
監督:横浜聡子
出演:駒井蓮、豊川悦司
黒川芽以、横田真悠、中島歩、古坂大魔王、
ジョナゴールド(りんご娘)、宇野祥平、西川洋子
6月18日(金)より青森先行上映
6月25日(金)より全国公開
2021/6/22