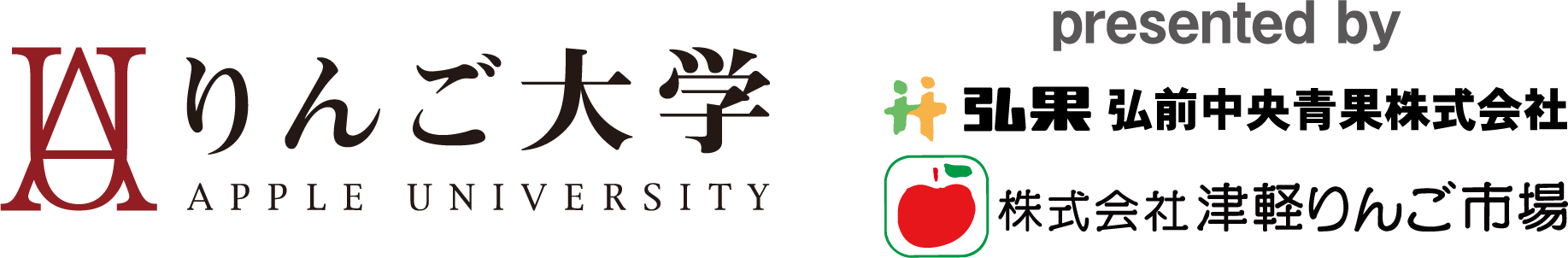Vol.14 パンを捏ね、ケーキを焼くこと

■パンとお菓子作りにはまった1年
このところ、毎日のように何かを捏ねては焼いている。「コロナ禍」という言葉が世間にあっというまに広まった今年の3月以降。スーパーやドラッグストアの棚からは、マスクに続き、トイレットペーパーやティッシュペーパーなど、生活必需品が次々に消えていった。さらに驚いたのは、小麦粉やホットケーキミックス、ベイキングパウダー、ドライイーストなどもたちどころに姿を消した。どうやらみんなが家にこもるようになり、パンやお菓子作りに精を出し始めたらしい。突然のように訪れたパン・お菓子作りブーム。かくいう私も、まんまとそのブームの仲間入りをした。
最初は、ちょっとパンでも作ってみようかな、くらいの軽い気持ちだった。買い物にも出かけづらくなった3月、4月。朝ごはん用の簡単なパンくらいなら、とネットで見つけたレシピをもとに、ごくごく簡単なパンを試しに作ってみた。出来上がったものはちょっと不格好だったけれど、焼き立てはやっぱり美味しい。それをきっかけに、もう少し高度なものを、形も改良して、と続けていて、気づけば道具が増えていった。そしてパンだけでは物足りないと手を出したのがお菓子作り。クッキー、チーズケーキ、チョコレートケーキ、パウンドケーキ。夫婦二人の生活なので、食べすぎないように気をつけつつも、ほぼ毎日、パン生地を捏ね、ケーキやクッキーを焼くようになった。ふたたびスーパーの棚に小麦粉が戻り、外出も以前のようにできるようになったあとも、習慣は変わらなかった。いまでも、私は毎日パンやお菓子を焼いている。
どうしてそんなに夢中になったのか、自分でもよくわからない。材料を軽量し、工程を間違えないよう集中しながら、粉を混ぜ、生地を捏ね、発酵させ、オーブンに入れて時間をはかる。その過程すべてが自分の日常のなかでリズムを刻み、気持ちがすっと落ち着いてくる。何かを無心で作る、という行為そのものが楽しいのかもしれない。原稿がうまく書けないときこそついパン作りに熱が入るのは、文字の代わりとなる何かを生産している気になるからなのか。
■ロンドンの洋菓子店を舞台にしたケーキ映画

そんな具合ですっかり新しい習慣に目覚めた私は、ついつい、パンやお菓子作りを描いた映画を探し求めてしまう。まず見つけたのは、現在公開中の『ノッティングヒルの洋菓子店』。監督はドイツ出身でイギリス在住のエリザ・シュローダー監督。以前、ロンドンのカップケーキ店の短編ドキュメンタリーを撮ったという彼女にとって、これが初長編劇映画。映画の舞台は、イギリスのノッティングヒルにオープンしたばかりの、一軒のパティスリー。店の名前は「ラブ・サラ」。だが店が開くまでには紆余曲折が。もともと、才能ある菓子職人サラと、その親友イザベラがふたりで始めようとしていたお店。だが開店当日、サラは不慮の事故で突然亡くなってしまう。残されたイザベラは、親友を失った悲しみと共に、莫大な店の借金を抱え、茫然とするばかり。そこに現れたのは、サラの娘クラリッサと、生前サラとは不仲だった母ミミ。母の死から立ち直れずにいるダンサー志望のクラリッサは、残された3人でサラ念願のお店をオープンしよう、それが母の一番の供養になるはずだと提案する。菓子職人のサラがいなければ無理だと当初は猛反対するイザベラも、やがてその熱意にほだされる。そこにサラの昔の恋人で、今はミシュランの二つ星レストランで働くパティシエのマチューが加わり、「ラブ・サラ」の開店準備は猛スピードで進んでいく。
マチューのつくるケーキは、さすが有名パティシエだけあり、どれも最高に美しく輝いている。りんごを使ったケーキもあるかも、と目を凝らしていると、青りんごのムースケーキが飛び込んでくる。丸くぽってりとしたフォルムに、真ん中にちょこんと載せられたチョコレートのへた。まるで青りんごをそのまま半分に切って並べたよう。こんなにかわいらしく美味しそうなケーキが並ぶなら、お店の成功もたやすいはず。だがそんな目論見は、開店そうそうに裏切られる。張り切って店を飾りつけ、最高のケーキを並べたというのに、オープンしても全然客が来ないのだ。
■さまざまな「故郷の味」を求めて

ケーキに問題はないはずなのになぜだろう、と悩むミミたちは、ふと街並みを見回し、自分たちの店に足りないものに気づかされる。ここはロンドン。住人の多くは、イギリス以外の国からやってきた人たちだ。となれば、他の店と同じ、いかにもヨーロッパ風のケーキだけでは店は流行らない。それよりも、住民たちそれぞれの「故郷の味」を取り入れれば、懐かしい味を求めてやってくる人も増え、ここは唯一無二の洋菓子店になるだろう。こうして「ラブ・サラ」では、大改革が始まる。街の人々にリクエストを募り、マチューたちはさまざまな国のお菓子をつくり始める。
人々が懐かしむ「故郷の味」。そのなかにはなんと日本の味も登場する。偶然コーヒーを飲みにやってきた日本人女性がリクエストするケーキの名前を聞き、少し驚いた。日本の定番ケーキならてっきりイチゴのショートケーキかと思いきや、注文されたのはなんと……。ここから先は、ぜひ実際の映画でご確認を。
この映画では、ただ店のサクセスストーリーが描かれるだけではない。サラを亡くした4人が、それぞれの方法でその痛みを乗り越えていく様が、お菓子作りの過程と共に描かれていく。最初は「私は経営に専念するだけ」とマチューひとりにケーキ作りを任せていたイザベルも、彼に促され、しぶしぶ厨房に足を踏み入れる。実はイザベルも、かつてはサラやマチューと一緒に製菓学校に通っていたのだ。久々にケーキ作りを再開したイザベラ。生地を捏ね、成形し、オーブンで焼く。クリームを練り、ていねいにデコレーションをする。ひとつひとつの作業を黙々とくりかえすうち、サラの喪失に暗く沈んでいた彼女の顔が徐々に輝きを取りもどす。
■停まっていた時間が動き出す

ケーキ職人の映画といえば、数年前に公開されたイスラエル映画『彼が愛したケーキ職人』も大好きな作品だ。こちらの映画も、物語はある人物の突然の死から幕を開ける。事故で亡くなったのはイスラエルで妻子と共に暮らすオーレン。だが彼には秘密があった。出張先のドイツ、ベルリンのカフェで働くケーキ職人トーマスと同性愛の関係にあったのだ。
物語は、オーレンの死を乗り越えられないトーマスの視点で語られていく。妻子ある男との恋。いわゆる「不義の関係」ゆえ、公に彼への追悼を示すこともできないトーマスは、亡き恋人の面影を求めて、彼の妻アナトがエルサレムで営むカフェへと向かう。自分の正体は明かさないまま、カフェで働きだしたトーマスは、アナトを手伝い、自分が得意なお菓子づくりを始める。だが彼の好意はすぐには受け入れられない。この地では非ユダヤ人はオーブンを使えないという厳格なルールがあり、勝手にクッキーを焼いたトーマスはアナトの兄から厳しく叱責されてしまう。そもそもユダヤ人が多く住むエルサレムの地で、ドイツ人のトーマスに向けられる視線は決して優しいとはいえない。それでも、夫を亡くし、一人で息子を育てながらカフェを経営するアナトは、無口だが誠実なトーマスに徐々に信頼を寄せていく。やがて彼がつくるケーキは評判となり、店は活気を取り戻す。映画のなかには、美味しそうなケーキやお菓子がたくさん登場する。ドイツ名物の黒い森のケーキ。オーレンが大好きだったジンジャークッキー。直接画面には登場しないけれど、アップルパイも評判のようだ。そういえば市場でりんごを買う姿も映っていた。トーマスがつくるのはドイツ流のアップルパイだろうか。
トーマスとアナトの関係も、徐々に親密さを増していく。カフェを経営してはいるけれど、ケーキやパン作りは得意じゃない、と言う彼女に、トーマスは自分のレシピを教え、生地作りのコツを教えていく。大事なのは生地の温度を一定に保つこと。手が冷たいと生地はうまく伸びてくれない。焦らず、ゆっくり生地を温めていけばいい。生地を捏ね、ていねいに伸ばしていく彼の手つきは、妙に官能的だ。それを横で見ているアナトの心にも、小さな炎が灯る。
同じ男を愛し、ある日突然、その存在を失った男と女。どれだけ心を通わせようと、ふたりは決して寄り添いあえない。ふたりが近づくのは、ただ厨房のなかでだけ。
ケーキ作りが人々の関係を変化させ、停滞していた時間を前に突き動かす。このふたつの映画は、どちらもその過程をていねいに描いていく。映画のなかには色とりどりのお菓子がずらりと並ぶ。映画を見ながら、自分でも新しいケーキに挑戦してみたくなる。年末年始には、りんごを使った豪勢なアップルパイを作ってみよう。
2020/12/24