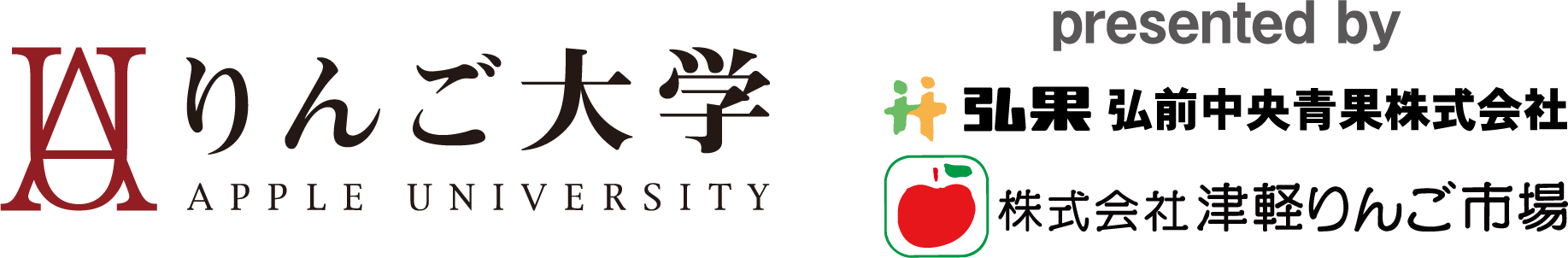File#③ 鳴海 信子 Nobuko Narumi
りんご農家に生まれ、結婚を機にりんごの行商を始め、長年りんごの販売を続けた女性がいます。鳴海信子(なるみのぶこ)、御年85歳です。
1932年(昭和7年)7月10日、8人兄弟の5番目に生まれた信子の生家は、弘前市下湯口でりんごを栽培している農家です。下湯口地区は弘前市の中で最もりんご栽培が盛んな地区の一つです。信子は幼い頃から背が高く、よく両親に農作業の手伝いを頼まれたそうです。兄たちは兵士として戦争に行っており、5歳上の姉はもう嫁いでいました。妹は小柄で弟はまだ幼かったため、背の高かった信子が必然的に手伝いをしていたのです。小学生の時から手伝いを始め、その後弘前和洋裁女学校(※現在の柴田女子高等学校)に入学したものの、家の農作業の手伝いが忙しかったため学校に行けない日も多く、あまり勉強はできなかったといいます。信子は「言いつけられたことはちゃんとやるし、飽きたといって逃げることもしなかったから、あてにされていたんだよね」と幼い頃を思い出しながら語ってくれました。
1949年(昭和24年)、信子は親のすすめで見合いをし、嫁ぐことになります。嫁ぎ先は弘前市大町でりんご屋を営んでいた鳴海家です。夫となる鳴海正尚は3人兄弟の三男で近衛兵として皇居で働いていました。もともとは信子の姉が正尚の長兄に嫁ぐことになっていたのですが、正尚の長兄、次兄とも戦争に行き、次兄は戦死、長兄は戦争が終わっても音信不通だったため、信子の姉は他の家に嫁ぎ、三男の正尚が家業を継ぐため弘前に呼び戻され、信子と見合い結婚をしたのです。1950年(昭和25年)には長女を出産し、平穏な生活をしていました。しかし、音信不通だった長兄が弘前に戻ってきたのです。それと同時に長兄も結婚し、家業も長兄が継ぐことになったため、信子一家はなかば強引に家を追いやられてしまいます。予測もつかない事態にとてもあわただしい生活を送っていましたが、1954年(昭和29年)、長男を出産したのを境にようやく落ち着きを取り戻しました。しかしその矢先、正尚の実家で食堂を始めることになり、また大町の実家に戻って食堂の手伝いをするようになりました。このように信子は数年で何度も正尚の実家に入ったり出たりを繰り返し、振り回されたといいます。
行商の始まり
信子は食堂の手伝いをしていましたが、嫁である信子に給料は無く、兄嫁との折り合いも悪かったため、居心地が悪いと感じていました。そんな中、夫の叔母が戦後の引き上げで弘前に戻ってくると、行商を始めることになります。鳴海信子23歳の時です。そもそも大町の実家では、食堂の他に新聞屋へ貸していた場所があり、新聞の仕分けなどをする台がありました。さらにそこを行商人の背負い籠を預かる場所にしており、行商人が頻繁に出入りをしていました。夫の叔母はその行商人たちと一緒に行商を始めたのです。信子は「実家(下湯口)にりんごもあるから、行商をした方がお金になるかと思ってね」と、なかば興味本位でその行商についていきました。これが、りんごを背負って商売をする背負子という行商を始めることとなったきっかけでした。
当時、青森と函館を結ぶ青函連絡船がありました。連絡船があったおかげで人々の行き来も多く、りんごがよく売れたそうです。信子は「連絡船があったときだからよく売れたんだよね。若いおなごが売ってるなんて珍しいからね」と、はにかみながら話してくれました。背負子と呼ばれる行商人は当時たくさんいましたが、信子のような若い女性は珍しかったのです。興味本位で始めた行商ですが、りんごが売れ、次第に楽しくなってきた信子はこのまま行商を続けようと思ったそうです。信子は「食堂手伝ってもお金くれないし、あの時はすごく儲けたからね」と笑い、話してくれました。

(右)信子が実際に使用していた背負い籠
はじめの頃は下湯口の実家からりんごを分けてもらっていました。自転車にりんご箱を2箱つけて大町まで約6キロの道のりを運び、それを背負って青森まで行商に行きました。そのうち弘前駅前に何軒かあった小売店からりんごを仕入れたり、大町からほど近い場所にあった大城東青果(※元の八百助青果)や大中青果(※現在の弘果弘前中央青果の前身)で競りに参加して買い付けるようになっていきました。買い付けたりんごは背負い籠に1箱分を入れ、その上に段ボール箱に入れたりんご1箱分、合計2箱分を背負い、青森市の駅前にある市場(小売店)に売りに行ったそうです。信子は直接お客さんに販売する小売りではなく、仲卸として小売店にりんごを卸していました。仕入れ値に1箱500円を上乗せして販売し、2箱売れれば利益が1,000円なので、その当時の作業労働の日当が男性は300円、女性は200円位でしたので、それに比べ儲けがよかったといいます。
こうして小売店にりんごを卸すとまた次の注文があり、徐々に注文数も増えてきます。その注文が多くなると1回の注文で何箱も持っていかなければなりません。トラックがまだ普及していなかったため、汽車で何箱分も運ぶことになりますが、信子一人では限界がありました。幸い信子の家は弘前駅から2軒目という近い場所にあり、注文を受けた何箱分ものりんごをリヤカーで駅まで持っていき、それを積んで青森まで行くことはできますが、青森駅から小売店まで運ぶのは無理がありました。そこで考えた信子は、何度も汽車で弘前と青森の往復をしているうちに、背負い籠専門に運んでくれる人たちの存在を知り、その人たちに配達をお願いすることにしたそうです。「その当時は背負い籠専門に運んでくれる人がいっぱいいてね、電話とかしなくてもだいたい何人か乗ってきてお願いしていたの」と信子が語るように、弘前と青森の間にある、浪岡駅や大釈迦駅でりんごを運んでくれる人が乗車してきたそうです。その人たちに汽車の中で運び先の指示をし、りんごを運んでもらっていたのです。背負い籠と段ボール箱に入れた合計2箱分のりんごを背負わせて運んでもらっていたそうです。手間賃として1箱100円、2箱で200円を払っていましたが、1箱売れると500円は儲けたため、1回行くだけで手間賃の1箱100円分を差し引いたとしても、だいぶ儲けることができたといいます。1日に2回青森に行くことも多くあり、忙しいながらもりんごが売れて儲けることの面白味を信子は感じていました。また、牛乳屋さんと知り合いになり、弘前から青森まで牛乳を運ぶトラックに、りんごをつけて運んでもらったこともありました。信子は要領がよかったのか、行商をしているうちに様々な人たちと知り合い、協力してもらいながら商売を続けていったのです。

行商をしていた頃の信子
夫の死~大黒柱として
1960年(昭和35年)、大町の実家から8畳1間程度の家を建てもらい、信子一家は実家を出て分家しました。夫の正尚は実家の食堂を手伝っていましたが、あまり商売には向かず、就職もうまくいかなかったため出稼ぎに出ていました。信子は子育てをしながら行商を続けていましたが、1964年(昭和39年)信子32歳の時、突然夫の正尚に先立たれてしまいます。脳卒中でした。信子は「一緒に背負子に行っても、自分の家がりんご屋だったから変なプライドがあって、背負子に負い目を感じていたのかね。それで結局出稼ぎにいったんだけど、前から血圧が高くても病院に行かなくてね。頑固な人だったからね」と悔やむような口調で話してくれました。夫が亡くなってからも悲しみに暮れる暇もなく、残された二人の子どもを養うため、信子は必死で商売をしました。

家族4人最後の写真(弘前観桜会にて)
1965年(昭和40年)、1トントラックを購入し、背負子からトラックで商売をするようになります。汽車の発車時間を気にせず、効率よく青森に行くことができるようになりました。商売は順調でしたが、りんごを買い付けていた大中青果では女性が一人で競りに参加するのはまだ珍しく、商売敵からは「リヤカーで来て邪魔だ」と馬鹿にされたそうです。周りを見てもまだ2トン車の大きいトラックは少なく、単にからかわれただけなのですが、そのように馬鹿にされ悔しい思いもしてきました。しかし、逆境を糧に信子は一家の大黒柱として必死に商売を続け、トラックもだんだんと大きいものに変えていきました。
こうして商売を続けてきた信子は、1968年(昭和43年)に自宅を新築しました。また、1971年(昭和46年)に弘前市城東に土地を購入し、倉庫と冷蔵庫も建て商売の幅を広げていきました。その時のことを信子は「私は銀行から借りることはしない考えでね、どんなに大きな買い物でもお金が貯まったら買っていたからね、その時はそんなに儲けていたんだろうね」とまるで他人事のように語りました。夫が亡くなってから10年足らずの間に自宅の新築と倉庫・冷蔵庫の建設を借り入れもなく出来たほど、商売が順調でした。それは、信子の並外れた努力が実を結んだ結果でもありました。
周りの協力があってこその商売継続
家族を支えなければという思いと同じく、商売の面白味を覚えたことで、信子はますます商売に情熱を注ぎました。信子は愛嬌があり人当たりもよく、自然と周りの人たちの協力を得ていました。いつものように朝4時頃に支度をして一度青森に行ってりんごを売り、注文を受けて8時の競りに間に合うように弘果(※前 大中青果)まで戻った時のことです。弘果ではりんごの売買取引は売り掛けだったため、青森で販売した分の現金が手元にありました。その現金を持ったまま競りに向かうのですが、時間がないのでトラックに現金を置いたまま競りに向かっていたといいます。それを見た当時の総務部長が、「車にただ置いておくだけだと盗まれるよ。競りが終わるまで預かっておくよ」と信子の財布を預かってくれたのです。そして競りが終わるとまた持ってきて、それ以降も信子を気にかけてくれていたそうです。「ずいぶん部長さんにはお世話になった」と当時を思い出しながら語ってくれました。
りんごの商売は当然のことながら、りんごが収穫される秋からが最も忙しく、人手も必要になります。高校卒業後に勤めに出ていた長女にも、10月頃になると手伝ってもらっていました。長女は勤めながらの手伝いは大変だったため、勤めてから1年半で辞め、信子と一緒に商売をするようになりました。
そんな中、りんごの商売も軌道にのっていた1972年(昭和47年)、いつものように長女がトラックを運転し2人で青森に向かう途中、追突事故をおこしてしまいます。信子は大怪我をしてしまい、生死の境を彷徨ったといいます。「三途の川を渡る手前まで行って、旦那か誰かにまだこっちに来てはだめだって言われて目が覚めたんだよ」と不思議な体験もしたそうです。入院中には、弘果の社長(当時)が自ら盛り籠を持ってお見舞いに来てくれたといい、「わざわざ社長さんにお見舞いに来てもらって、嬉しいやら申し訳ないやら…」としみじみ語りました。しかしこの時信子は、「ちょうど息子も高校3年の終わりで就職も決まったし、もう商売をやめよう」と思いはじめていました。
8か月間入院し商売ができなくなったので、倉庫は他の人に貸し、退院してもリハビリや自宅療養をしていたため、商売は完全に休んでいました。1年ほどリハビリと自宅療養で過ごし怪我も回復してきた頃、信子の元気な姿を見た弘果の常務(当時)が、「そんなに元気になったのだから、青森の青果市場の1区画を借りて、そこで商売をすればいい。電話をくれればトラックを出してりんごを運んでやるから」と、もう一度商売をするように話したそうです。時を同じくして、得意先からも次々と注文が入るようになりました。もともと商売をやめるつもりだった信子ですが、やめていられない状況となったのです。そこで信子は、弘果からの店を出す話は遠慮したもののトラックを借りることには甘え、実兄にも協力してもらいながらまた少しずつ商売を始めました。しばらく実兄と一緒に商売をしているうちに、信子も普段通りの動きができるようになり、同時に注文も増えてきたので、もう一度本格的に自らの商売を始めることになりました。

(右)自宅前にて
再び商売を始め、面白味を思い出した信子は、さらに精力的に商売をしました。青函連絡船と転勤族の多かったその当時は、やはりりんごはよく売れたそうです。当時のりんごは“千成(紅玉)”と“雪の下(国光)”が主流で値段もある程度決まっていましたが、信子は“スターキング”や“デリシャス”、“ゴールデン”の完熟したりんごを販売していました。これらの新しい品種は今でいう訳ありりんごであっても、試食をさせると味は抜群においしかったため飛ぶように売れたそうです。“紅玉”や“国光”よりも決まった値段もなかったので儲けが大きかったのです。青函連絡船が本州と北海道を結ぶ重要な交通手段だった当時は、午後3時から翌朝6時頃までの夜間に営業している店が数件ありました。信子は朝の商売の他に夜間営業している店にもりんごを売りにいったそうで寝る間も惜しんで働いていました。りんごが収穫される時期は十和田湖の紅葉も見頃となり、観光客も多く訪れるため土産用のりんごもよく売れ、りんごが収穫される10月から、お歳暮の時期の12月までで1年分の収入を得られていたといいます。
大怪我からの復帰後、さまざまな思いをしながらも商売を続けてきた当時のことを信子は「本当に市場の皆様にはお世話になった。入院中は社長さんがわざわざお見舞いに来てくれたり、その後も結局は断ったけれども、青森に店出せばいいって言ってくれたしね。市場の皆様のおかげで続けてこれたようなものだよ」と思い出しながら語ってくれました。
事故で怪我をして以来やめるつもりでいた信子ですが、周りの人たちの協力を得て商売を続けてきました。当時は就職をした長男も長女の時と同じように、秋になると手伝わせていました。朝に一度青森に行くと時間通りに戻ることができないこともあり、よく会社に遅刻をしていたそうです。信子は「休みの日だけ手伝わせていたつもりだったんだけど、平日も手伝わせていたんだろうね。子どもたちを犠牲にしてしまったね」と申し訳なさそうに語りました。そのうちに長男も会社を辞め本格的に手伝うようになり、1979年(昭和54年)には鳴海商店としての営業をスタートします。それと共に長女もまた手伝うようになりました。
信子には不思議と人を惹きつける力があるのか、信子を気にかけ協力してくれる人が自然と集まっていました。それにおごることなく、感謝の気持ちを忘れず、常に懸命に働く姿が信子の魅力なのかもしれません。
努力と神頼み
信子が夫亡き後も女手一つで子育てと商売を続けてこられたのは、神信仰も理由の一つにありました。「兄弟にも相談できないの。いくら兄弟でも(商売が)よければ妬むし、悪ければ笑うし。男にも頼らないで、神様を信じて相談してるの。それと自分の判断と」と信子はいいます。実家(下湯口)近くの出雲大社弘前分院に、信子の実兄(次兄)が神主として養子、さらに実姉が嫁いだことで親戚となった縁もあり、仕入れの時にはいつも出向き「売れるりんごを買わせてください」と神頼みをしていたそうです。信子が売るりんごは他より値段が高いので、小売店では仕入れを躊躇するのですが、いざ店に並べると、不思議なことに信子のりんごがよく売れたといいます。市場での競りでは皆競争で、他の人が安くて良いりんごを買っていっても、なぜか信子のりんごがよく売れ「これも神様のおかげなのかな、だからあの事故でも助けられたのかもしれないね」と笑いました。
しかし、ただ神頼みだけをしていた訳ではありません。毎日競りに行き、良いりんごを買うために競りが始まるより前に市場に行き、必ず下見をしていました。信子が目を付ける土産用(贈答用)りんごは商売敵も多く、値がつり上がったり落札できないこともありましたが、信子は市場内を駆け回りながらりんごを買い付けていたのです。いつも一生懸命に商売と向き合い、協力してくれる人たちへの感謝も忘れず、良いりんごを仕入れるための努力は惜しみませんでした。
こうして信子自身の商才と努力、さらには神信仰によって鳴海商店を切り盛りしていきました。その後長男も結婚し孫も生まれ、時にはりんごを積んだトラックで孫の保育園に迎えに行ったり、長男夫婦とも一緒に商売を続けてきました。
1994年(平成6年)に病気で胃の手術をすることになり、商売から身を引くことになりますが、それまで長男と共にりんごを売り続けてきたのです。
現在 家族のために祈る日々
信子の長女の野呂節子さんは、結婚・出産後も信子を手伝い、りんごの商売を共にしてきました。「就職したのに手伝わされて結局辞めて、朝4時に起こされてトラック運転して事故起こして。鳴海商店になってからも結局運転手がいないからって手伝うことになって、母には振り回されました」というものの、その表情に怒りなどはなく、「母の商売のおかげでお金の不自由を感じたことはなくとても感謝しています。それと、昔から母はきれい好きで、料理、縫い物、編み物が上手で女性としても尊敬しています」と、穏やかなまなざしで信子を見つめていました。
長男の鳴海正剛さんは現在、鳴海商店を引き継ぎながらもさらに商売の幅を広げ、株式会社スノウプルの代表取締役社長として信子の意志を受け継いでいます。正剛さんは小学4年生の時に父親を亡くし、6年生頃になると信子の手伝いをしていたそうで、幼い頃のことを「まだ手伝いができない小さい時は、実家(下湯口)に預けられたこともありましたけど、母が一生懸命商売してくれたおかげで、周りの人から良くしてもらって寂しい思いもせずにいれましたし、父親がいないコンプレックスも感じたことはありませんでした」と話してくれました。また、商売人としての信子のことを「当時は、商売の幅を広げていくような行商人がほとんどいない中で、母は商売の幅を広げ大きくしてきました。だいぶ苦労もしてきたようですけど、ずっと継続して商売をしてきてくれたおかげで、今私もこうして商売することができています。それと、商売の基礎も母から教わってきました。仕入れ時の丁寧な下見は母がずっと続けてきたことですが、これは今でも私が一番大事にしていることです。本当に感謝していますよ」と話し、母親としても商売人としても尊敬しています。
信子はそんな長男のことを「小さい頃から本当によく手伝ってくれる親孝行な子で、母親が背負子でも恥ずかしがることなく友達に紹介してくれてね。最近は珍しい果物を持ってきてくれたり気にかけてくれるの。息子が今でも商売を続けてくれているおかげで今すごく幸せなんだよ」と誇らしげに語ってくれました。

(右)鳴海商店倉庫前にて
株式会社スノウプルは社長の正剛さんと奥様の静子さん、さらに2人の息子さんが家族ぐるみで支え合って商売をしています。株式会社スノウプルは全国のスーパーマーケットにりんごを卸していることもあり、日曜日でも休みなく懸命に働いてきました。その姿は信子の商売人としての血が受け継がれている証ではないでしょうか。また、奥様の静子さんの内助の功によるものも多く、まさに家族の絆といえるでしょう。
商売を長男に委ねてからも、しばらくは商売のことが気になり、時々顔を出していたそうです。その時に長男や従業員たちに食べさせるため、漬物やいなり寿司、餅類などを作ってもっていくと大変喜ばれたといいます。「年寄りの作ったものって若い人あまり食べないじゃない。だけど嫁さんでも孫でも美味しいってよく食べてくれるの」と信子は嬉しそうにいいます。料理や花の寄せ植えに夢中になり、手料理を振舞ったり自宅の玄関先を鉢植えでいっぱいに飾ったりと、引退後も楽しく過ごしていました。
最近はマッサージなどに通い、健康に気遣いながら生活しています。商売をしていた時からの習慣である、毎朝神棚に拝むことも忘れません。家族の健康、商売繁盛、長男の夫婦仲良くと、自分の分の神頼みは二の次。そんな信子だからこそ長男夫婦に慕われ、時々外食に誘われるそうです。「もう足腰弱くなったから誘わなくてもいいって言ってるんだけどもね」と笑っていいますが、家族を犠牲にしてまで必死に商売を続けた信子は、ようやく今穏やかな生活を送れる幸せを感じているのです。

(右)子、孫、ひ孫に囲まれて
2017年(平成29年)5~6月執筆
2017年(平成29年)8月公開
プロフィール : 鳴海 信子(Nobuko Narumi)