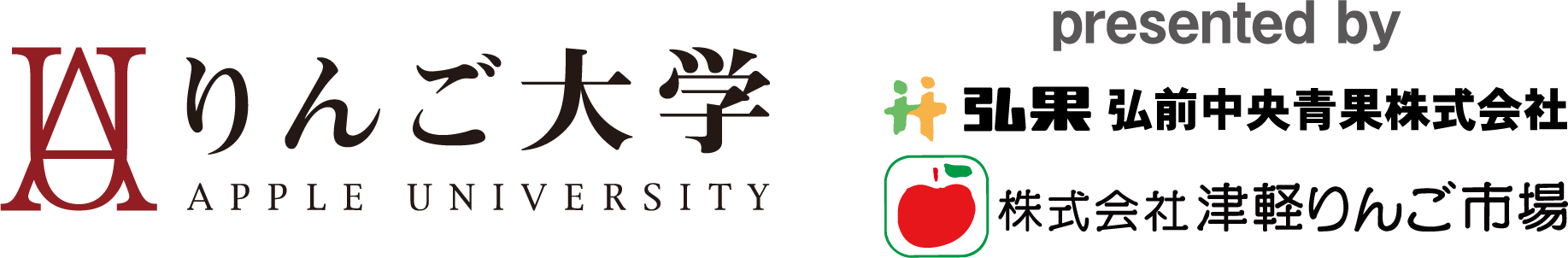File#① 小山内 政史 Masashi Osanai
標高約300メートル。青森県のりんご栽培地としては1、2の最高地に位置する大鰐町駒ノ台地区。高地は平地とは異なり傾斜地が多いため、作業面の効率が悪く、さらに雪が多く剪定作業も一苦労となります。また、りんご栽培は寒暖の差を必要としますが、高地は「寒」が多く「暖」が少なくなるので実が小ぶりになることが多くなります。その反面、「寒」のおかげで着色がよく、実が締った味のよいりんごがとれ、もちもよく、長期冷蔵に向いていることから人気があります。しかし、作り手からすると収穫量が伸びないことが悩みの種となります。
小山内政史(おさないまさし)は、この地で約60年に渡ってりんご栽培に取り組んできました。見晴らしのよい集落の入口に辿りつくと、すぐに看板と石碑が二つ並んで目に飛び込んできます。看板には「フロンティアスピリット駒ノ台」の文字。そして石碑には、理想郷を夢見てこの地にやってきた若き開拓者たちの思いが刻まれています。
1936年(昭和11年)、小山内は6人兄弟の長男として産声を上げました。世はまさに戦争真っ只中の激動の時代。小山内の父はそんな中、開拓者の一人として駒ノ台の地に根を下ろすこととなりました。駒ノ台は総世帯数30ほどの山あいの小さな集落。一番近い小学校まで歩いて1時間以上もかかる場所です。わんぱく坊主の小山内は、小学校卒業後そのまま家の手伝いに入りました。開拓直後だったため農作業にも不便なことが多く、「手押しポンプをその場所まで担いで薬かけをしていた」そうです。
当初はじゃがいもや大豆など、あらゆる種類の野菜を栽培していましたが、数年後からりんご栽培に着手し、昔ながらの品種(当時の主力品種)である“千成(紅玉)”と“雪の下(国光)”を植えていきました。父のあとを継ぐ形で、小山内もりんご栽培に携わるようになりましたが、最初はりんごに対する思い入れが特にあったわけではなく、「自然体でやっていた」そうです。
次第に入植者の子ども、いわゆる二世たちが中心になり、集落全体でりんご栽培に力を入れるようになっていきました。しかし、山間のこの場所は独特の地形。まだ原野だった当時は、とにかく風の強さに悩まされました。特に『やませ』と呼ばれる冷たい東風の影響は深刻で、開花は遅れ実は落ち、落ちずに残った実も傷だらけということが数知れず。
「ここはりんご作りに関しては災難な場所なんだ」
それでも、杉や松などの防風林を大量に植え、誰一人音を上げることなくりんご栽培と真っ直ぐに向かい合ってきたのです。
ここでしかできないことがきっとある
岩木山のふもと船沢地区で“スターキング”を栽培し成功を収めた對馬竹五郎氏の話を耳にしたのは、昭和47・8年頃の30代後半でした。對馬氏は、東京銀座の高級果実店千疋屋 斎藤義政氏がアメリカから取り寄せた2本の“スターキングデリシャス”の苗木の栽培を依頼され、その育成に成功し、それまで全盛だった“紅玉”や“国光”をしのぎ、船沢に『スターキング時代』を作り上げたのです。
「自分もこの山のてっぺんで何かがしたい」
その矢先、りんごにかける袋を買いに行った時のこと。袋屋の社長は、「まだ“紅玉”や“ 国光 ”を作っているのか」と馬鹿にして笑ったのです。小山内の心に完全に火が付きました。このままではいけない。何かしなければ何も変わらない。
通常、平地と呼ばれる土地よりも、小玉傾向で収量で劣る山手で作るには、山手の特徴である“寒暖の差”を利用した色付きの良さと、山手でも大玉になる品種の選定が必要でした。そこで小山内が目をつけたのは“陸奥”でした。その頃“陸奥”はすでに下火。小山内は元々青りんごであった
“陸奥”を現在の袋かけ栽培となった指導者的存在であり、まさに先駆者なのです。常に挑戦し続けることを厭わない開拓者精神。小山内は、脇目も振らず“陸奥”の栽培に取り組んでいきました。
“陸奥”は袋かけを2回行わなければならず、手間暇を必要とする品種です。美しく着色させるのも難しいのです。しかし“陸奥”は、駒ノ台というこの高地独特の気候に合っていました。そして他のどのりんごとも違う、“陸奥”独特の美しい薔薇色。小山内はいつしか“陸奥”にすっかり魅了されていました。
「自分だけではなく、あの頃は作る方も売る方も買う方も皆りんごに対する夢を持っていた」
決してでしゃばることはありませんが行動力があり面倒見の良い小山内は、気が付けば集落のリーダー的存在として仲間をまとめ、励まし、支えてきました。「誰かが先頭切ってやらなければならないからね」小山内を中心に、駒ノ台の仲間は団結し意欲的に“陸奥”を育てました。やがて駒ノ台でとれる“陸奥”の色づきの良さが噂になり、好評価を得るようになったのです。収穫期には市場で“陸奥”の大量販売、通称『むつまつり』が開催され、大盛況を博しました。特に駒ノ台産は一目置かれ、高値で取引されました。
小山内は駒ノ台のリーダーから弘果りんご連絡協議会2代目会長に就任し、頼れる存在として内外から慕われ津軽のりんご生産者の先頭に立ち引っ張っていったのです。

“陸奥”について詳しくはこちら

(右)平成元年 弘果大忘年会にて(写真中央が小山内)。
自然の力には勝てない
小山内55歳。会長任期中の1991年(平成3年)9月28日早朝、かつてない大型台風19号が津軽地方を襲いました。通称『りんご台風』です。最大瞬間風速50メートルを越える強風で、津軽地方全域に大きな爪痕を残したのです。町のいたるところで電柱が倒れ、建物が損壊し、トタン屋根が飛んでしまうほどのかつてない強烈な台風。
「朝5時に畑を見に行った時は何ともなかった」
しかしその数時間後再び畑に戻ると、目を覆いたくなるような光景が広がっていました。
「棒で枝を叩いたって簡単に落ちたりしないのに、よくもああきれいに落ちるもんだと思ったよ」
“陸奥”は、壊滅的な被害を受けたのです。しかも共済に入っていなかったため、収入はほぼゼロ。もちろん周囲の仲間たちも例外ではありません。それでも、りんご農家をやめる者は一人もいませんでした。互いに支え合い助け合って、どうにかその年は乗り切りました。その後台風に備え防風網を設置したりしたものの、山間の独特の地形の中でりんごを作る難しさを、改めて思い知らされたのです。

それから23年後の2014年(平成26年)9月12日、津軽地方に大粒の雹が降りました。駒ノ台一帯もその被害に遭い、翌日の午前中にも雹は溶けずに畑一面を埋め尽くし、収穫まであと1ヶ月余りのりんごにも傷がついてしまいました(雹害のりんごは価格が安くなります)。
それでも小山内は、障害があってもこのまま捨てるわけにはいかないと、すべて玉まわしをして大事に育てました。樹の下から見ると雹による傷の状態はあまり分かりませんでしたが、収穫してみるとほとんどの実に傷がついていました。
「よっぽど大きいのが降ってきたんだ、と思ったよ」と小山内は振り返ります。はしごに登って上から見ると、雹の傷跡が枝にもついていました。
再び襲い掛かった自然の猛威に、またしても無力であると思い知らされましたが、小山内は雹の傷がついたりんごでも味を落とすことなく見事に育て上げ、かなりの減収にはなったものの、厳しい1年をなんとか乗り切りました。
こうして毎年自然と戦いながら、りんごと向き合ってきたのです。
新品種“大紅栄”に挑戦あるのみ
りんご台風を経て、小山内は今後の方向性を模索していました。雪深い高地駒ノ台は花の開花が10日以上も遅く、秋までの玉伸びが鈍いことから、主力品種は平地に比べて小玉傾向となるのが悩みでした。そこで高地の気候に合った大玉品種の“陸奥”の栽培は成功を収めましたが、手間ひまがかかり生産者の負担が大きく、“陸奥”は下火傾向となっていました。もっと省力生産のできる“陸奥”にかわる品種はないものか。
そんな中、とあるりんご園に研修に通っていた長男が、そこの園主からたまたま数本のりんごの枝を託され持ち帰ってきました。“大紅栄”との出会いです。
「どんなりんごなのかろくに見もしないで栽培を決めた」
豪快に高笑い。小学校卒業と同時にそのまま就農した時や、下火になっていた“陸奥”を植え始めた時と同じです。やると決めたらとことんやる。迷いは全くありませんでした。一種の賭けのような状況の中、小山内はもらった枝を接ぎ木して大切に育てました。数年後の結果を心待ちにしながら。
そして小山内の勘に狂いはありませんでした。“大紅栄”は着色がよい高地の気候に合う品種だったのです。
「“大紅栄”は見た目も食味も皆いい。これは絶対“陸奥”の代わりになると確信した」
事実、現在の“大紅栄”の全体数量も約1,200トンまでと、“陸奥”と肩を並べるほどの生産量となりました。
生産者にとってありがたいことに、“大紅栄”は袋かけをする必要がなく管理に手がかかりません。さらに山間の地で作る“大紅栄”は、寒暖の差がうまく作用し着色が良く味が濃い。すでに還暦を超えていた小山内は残りの人生を“大紅栄”と共に過ごす決心を固めたのです。

自分で探し自分で考える
『りんごにも山向き、平地向きの品種がある』
平地に比べ雪の量が多い山の園地では、葉のある樹は雪害に見舞われてしまいます。小山内は園地の品種構成の重要性を語ってくれました。
「その土地がらにあった品種を栽培することが最も重要で、今の畑を見ていると品種がばらけ過ぎているところが多い」
土地の利を活かした品種の栽培は不可欠です。やみくもにあらゆる品種を育てるのではなく、
「もし栽培に多少手間がかかるとしても、それぞれの地域に合った品種というものが必ずある。それは自分で探すしかない」
そして見つけた“大紅栄”。
また、何よりりんご栽培に欠かせないものがあると小山内は言います。
「仲間との協力がないとりんごを作っていけない。互いに声をかけ合って、苦しい時には支えあう。だから頑張れるし、いいりんごができる」
冬には雪が1m半~2mも積もる高地。学術的には、りんご作りが不可能な場所とまで言われています。それでも開拓者精神を失わず、同じ志を持つ仲間と共に、自然と共存しているのです。

(右)現在の大紅栄のりんご畑。
家族と仲間
現在80歳。若い時分よりカメラに興味があり、風景を中心に撮り歩いていました。また、集落の仲間やその家族をカメラに収めては、写真をプレゼントしていました。50代の頃には、黒石よされ写真コンテストで入賞したほどの腕前です。
最近の休日はもっぱらのんびりと過ごすことが多いのですが、楽しみの一つが温泉巡りです。特に、毎日のように足しげく通うのは大鰐町の『鰐come(わにかむ)』。小山内がお気に入りのその温泉を営むのは、同じ駒ノ台でりんご栽培を続ける八木橋孝男氏。何十年も、同じ地で同じ苦しみや喜びを共有してきた旧知の間柄です。
「とにかく植物の観察力がずば抜けている。そしてこうと決めたらその信念を決して曲げない人」
感心と尊敬の念を込めて語る八木橋氏。かと思えば、
「あの人は典型的な津軽のじょっぱり(意地っ張り)だね。本当に頑固」
旧友ならではの少し冷やかすような調子で笑い飛ばします。共に苦労を重ねてきた気のおけない友人との交流もまた、小山内の原動力の一つなのです。
“大紅栄”の成長を見届けるのが楽しくて仕方ない今、元気に仕事を続けていくためにも身体のケアは怠りません。
そして、元気の源は酒と歌。
焼酎をちびりちびりとやりながら、大好きな歌謡番組を見るのが至福のひと時です。連絡協議会会長時代には、忘年会となると必ず自慢ののどを披露し場を盛り上げていました。
50年以上連れ添った愛妻と、跡を継いで農家の道を選んだ長男と共に、家族一丸となって仕事に精を出す日々。
「うちだけじゃない、駒ノ台のほとんどの家は三世も一緒にりんごを作っている」
親から子へ、子から孫へと受け継がれる開拓者の熱い思い。しかし若者に対しては特に口を出さずに、相談に来た時にだけ少々アドバイスをする程度だと言います。
「それぞれの考え方でやっていけばいい」
己の道は己の意思で決める。
常に挑戦し続け、自分で考えて行動し結果を出してきた小山内だからこそ言える重みのある言葉ではないでしょうか。
穏やかな優しい笑顔ながら、その瞳の奥からは若者と変わらず強くたくましい光が放たれていました。

(右)50年以上連れ添い支えてくれた妻に感謝してもしきれない。

2016年(平成28年)11月執筆公開
プロフィール : 小山内 政史(Masashi Osanai)