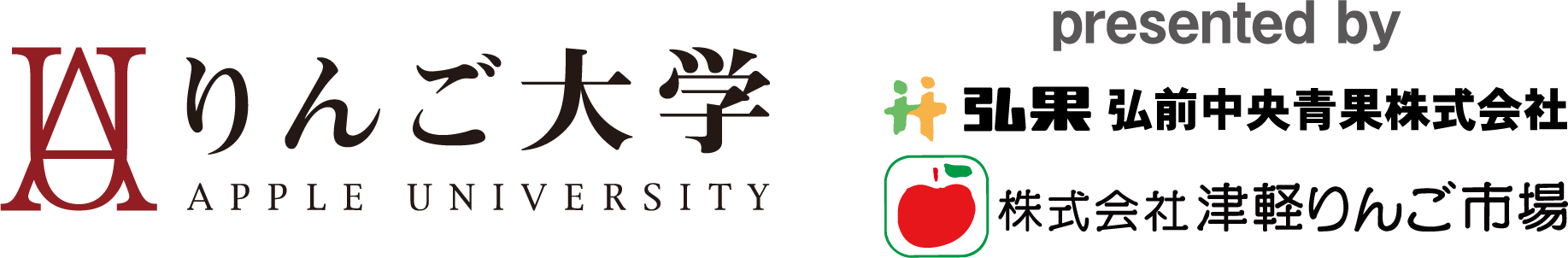Vol.18 最後の晩餐で食べる特別なりんご

■カルト的な人気を誇るSF映画『ソイレント・グリーン』
コロナ禍で滅入ってばかりの毎日。そんなときに見る映画は、できるだけ明るいものがいい。せめてフィクションのなかだけでも幸福な今を見たい。その一方で、より暗く、救いようのない現実をこそ見たいとも思う。たとえば救いのない人類滅亡物語や、腐敗しきった政府によって市民が犠牲になる政治劇。より悲惨さを求めてしまうのはなぜなのか。もしかすると、現実の酷さに辟易するからこそ、それを凌駕する悲劇を見たいのかもしれない。映画はときに、矛盾した欲望を引き起こすものだから。
近未来を舞台にした『ソイレント・グリーン』(1973年)は、まさにそんな気分で見るにはうってつけの映画。いわゆる人類の終末を描いたアメリカ製SF映画で、その後味の悪さと皮肉な物語展開が、カルト的な人気をもつ作品だ。監督は『ミクロの決死圏』(1966年)『絞殺魔』(1968年)を手がけたリチャード・フライシャーで、SF作家ハリイ・ハリスンの『人間がいっぱい』を原作としている。
物語の舞台は2022年のニューヨーク。人口が爆発的に増え、気候変動で環境が破壊されたこの世界では、深刻な食料危機に陥っている。貧富の差はますます広がり、一般市民はみな、電気もろくに通らない家で暮らしている。食糧難は危機的で、人々は政府から週一回配給される四角い固形の栄養食品「ソイレント」を食べ、どうにか日々を過ごしている。本物の食料はいまや高級品となり、ありつけるのは一部の特権階級だけ。そんななか、ソイレント社の幹部サイモンソン(ジョセフ・コットン)が、自宅の豪邸で何者かに惨殺される。会社は、近頃、海中プランクトンが原材料だという画期的な新製品「ソイレント・グリーン」を発表したばかり。いったい彼の身に何が起きたのか。物語は、この謎の殺人事件から幕を開ける。
■2022年、ニューヨークの食事情

事件を捜査するのは、殺人課の刑事ソーン(チャールトン・ヘストン)。彼はソイレントだけで生き延びてきた世代で、本物の食べ物など、目にしたことも口にしたこともない。サイモンソンの家で冷蔵庫に隠されたステーキ肉や新鮮な野菜を発見すると、ソーンは役得とばかりにそれらを自宅へ持って帰る。刑事とはいえ薄給の身。これくらいのズルは許されて当然、というわけだ。
ソーンが住むアパートには、少し風変わりだが知識豊かな老人ソル・ロス(エドワード・G・ロビンソン)が住んでいる。彼は食料が配給制になる前の世界を知る貴重な世代。すでに世間から姿を消した大量の書物を持つソルは、ソーンの「ブック=生き字引き」として捜査の手助けをしている。いつも「昔はこんな世界じゃなかった」と嘆くソル。ソーンは老人の毎度のぼやきに呆れながら、彼の類稀な知識には一目置いている。
ある日、事件を調べてもらうお礼として、ソーンはサイモンソンの家から盗んできた一冊の本と食料品をソルに渡す。ブランデー、牛肉、セロリ、そして新鮮なりんご。何十年も目にしていなかった食べ物を前に、ソルは「信じられない」と歓喜の涙を流す。この世界で本物の食べ物を目にするのは、奇跡に近い出来事なのだ。
ソルの調査により、ソーンは、ソイレント社の抱える何らかの秘密が、サイモンソン殺害に関連しているらしいと気づく。事件の裏には、巨大な陰謀があるようだ。俄然張り切り、力づくで関係者を取り調べていくソーン。だが上司からは、なぜかただの強盗事件として片付けるよう強制されてしまう。それでも捜査を続けるうち、ソーンは何者かから命を狙われるようになる。また彼は、サイモンソンが「家具」として保有していた美しい女性シャール(リー・テイラー=ヤング)に惹かれていく。ただしシャールはあくまで「家具」。この世界では、見た目の美しい女性たちは、裕福な男に買われることで生計を立てているのだ。シャールもまた、野性味あふれるソーンに惹かれるが、すべてを捨て、貧乏な暮らしを選ぶほどの覚悟はない。二人の淡い恋愛関係は、現実を前に悲しい結末へと向かっていく。
■『ソイレント・グリーン』に隠された恐るべき真実

同じ「ブック=生き字引き」仲間とソイレント社について調べていたソルは、ついに真実へとたどり着く。会社が隠していたのは、想像以上に恐ろしい秘密だった。知らずにはいられない、けれど決して知りたくはなかった真実。ソルは絶望し、ある場所へ向かう。「ホーム」と呼ばれるその場所は、いわゆる安楽死施設。自ら死を望んだソルを止めるため慌てて「ホーム」へ向かったソーンは、年老いた旧友から驚愕の真実を知らされる。
ソイレント社が抱えた真実とは何なのか? ソーンたちの生きる社会の根底には何が隠されているのか? 映画は、謎を追求しながら、社会が抱える闇を否応なく暴き出す。2022年の地球を逼迫する人口増加や食糧難は、あくまでもSFの世界での話。けれど、私たちにとってこれはただの絵空事ではない。深刻な環境汚染とそれに伴う気候変動によって地球が壊れていく様を、私たちは日々目にしているのだから。
『ソイレント・グリーン』は、社会のなかで隠された現実を、人々に見せつける。私たちが手にするものが一体どこからやってきたのか。工場のベルトコンベアによって運ばれていく材料が、どのようにして製品へと姿を変えるのか。誰もその過程を見ようとはしないけれど、そこには重要な真実がある。知るにはあまりにも残酷な事実。それでも私たちは現実を見なければいけない。やがて映画は、意味深なラストシーンによって幕を閉じる。その先に何が起こるのかは、見るものが想像するしかない。
■二人が味わったツヤツヤのりんご

陰鬱な物語のなかで、ソーンとソルが唯一本当に幸せな時間を過ごすシーンがある。サイモンソンの家から持ち帰った材料をもとに、ソルがフルコースを用意し、ふたりで食事をする場面。隠しておいたとっておきのカトラリーを広げ、手料理を披露するソルの顔は実に満足げ。まずはサラダを食し、次に牛肉を煮込んだメイン料理。料理と合わせるのはこちらも本物のブランデー。ゆっくりとその味を楽しんだ二人は、最後、デザートへと手をつける。ツヤツヤに磨かれた小ぶりのりんごが二つ。思い切って噛み付いたソーンは、その瑞々しい果肉にしばし茫然とする。一方ソルは、同じように噛み付いたものの衰えた歯では噛みきれず、残念そうに、ナイフで少しずつりんごを削っていく。その顔には、「若い頃は俺だって」という悔しさが滲んで見える。
それぞれの方法でデザートを食べきった二人。手元に残ったのは小さなヘタだけ。あまりの美味しさに芯も食べ尽くしてしまったのだろう。満足げに笑うソーンの前で、ソルは少しだけ寂しげだ。昔はこんな食事は当たり前だった。それがどうしてこれほど難しくなってしまったのか。もはや二度とありつけないだろう、一夜だけの特別なディナー。この最後の晩餐で口にするのが、人類が初めて食した果実と言われるりんごなのは、なんとも皮肉的だ。
劇中で強い印象を残すソル役を演じたのは、『犯罪王リコ』(1930年)をはじめ、1930年代、数々のギャング映画に主演し人気を博した名優エドワード・G・ロビンソン。40年代後期、ハリウッドで共産主義者を一掃しようとする「赤狩り」旋風が巻き起こった際、ロビンソンはブラックリストに記載され、その影響から映画俳優としては低迷することになった。ある意味で、激動の俳優人生を歩んだ人といえる。それでもブロードウェイに拠点を移し活躍を続けたあと、晩年はいくつかの映画に再び出演する。1973年1月26日に死去。遺作となった『ソイレント・グリーン』には、ロビンソン自身が歩んできた苦難の人生がたしかに刻み込まれている。

U-NEXTにて配信中
監督:リチャード・フライシャー
出演:チャールトン・ヘストン、エドワード・G・ロビンソン、リー・テイラー=ヤング、チャック・コナーズ、ジョセフ・コットン
2021/8/17